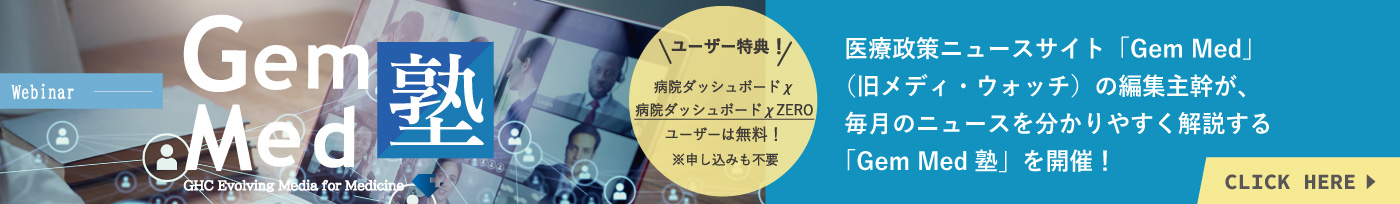主治医との信頼関係なくして、最善の医療なし―「プロ患者」に聞く正しいがん治療(1)
2017.9.11.(月)
39歳のときに大腸がんが発覚し、肝臓や肺へ転移を繰り返しながらも、6度の手術を経て完治した闘病生活を克明に記した『がん六回、人生全快』。著者で日本対がん協会の関原健夫氏は、医療者と患者の情報非対称性がある中で、どのようにして誤った情報に踊らされず、賢い患者として振る舞うことができたのでしょうか。また、日米のがん医療を経験し、どのような問題意識を持たれたのでしょうか――。「プロ患者」として知られる関原氏に聞きました(聞き手は米国グローバルヘルス財団理事長・アキよしかわ)。
オープンにしづらい「がんという病」
――関原さんは、6度の手術という過酷な闘病生活を繰り返しながら、銀行員としてのキャリアを全うされました。現在は日本対がん協会での活動が主軸なのでしょうか。
70歳を超えたので、当初は完全リタイアのつもりでいたのですが、未だに友人などから相談を受けることも多く、いくつかの組織で顧問や監査役なども引き受けています。中にはベンチャー企業から相談を受けることもあり、役職もなく無償でこうした相談に応じたりもしています。さらには、友人・知人経由で患者やその家族からの相談も絶えません。

関原健夫(せきはら・たけお)氏:1945年生まれ。京都大学法学部卒業。日本興業銀行(当時)ニューヨーク支店営業課長の時に大腸がんが見つかり、肝転移・肺転移で計6回の手術を受け、5年生存率20%といわれたがんを克服。みずほ信託銀行副社長、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社取締役社長などを歴任。中央社会保険医療協議会の公益委員、がん対策推進協議会委員などでも活躍し、現在は日本対がん協会常務理事を務める。
さまざまな相談に応じていて思うのが、がんは「がんになった」という事実をオープンにしづらいということです。背景には、「がんという病」への社会での認識不足があり、患者も過度に慎重になり過ぎるからです。これは病気に限らないことですが、「人と違うものを避けたい、排除したい」「異質なものだから特別扱いしよう」というある種の差別や区別の力学が働くからではないでしょうか。
例えば、働き盛りの男性ががんになった場合、患者自らそういう空気を感じて「社会のレールから外れてしまう」と思い込み、「隠せるものなら隠し通そう」と考えてしまう人も少なくありません。がんを秘め事にしておきたいする傾向は、万国共通のものでしょうが、特に日本ではその傾向が強いと感じます。がん患者になったことを明かしても、特に不自由なく働き続けることができ、周囲も格別差別することなく接してくれた私はラッキーだったと思います。
――ご著書では、職場でがんになったことを明かした際、積極的に励ましの言葉を投げかけてくる米国人と、控えめ、あるいは何も言わない日本人との反応の違いに戸惑った様子が描かれています。
思ってはいても口に出さないのは、日本人の特徴の一つでしょう。確かに、「阿吽の呼吸」という日本の文化の良さもありますが、生死にかかわるような人生の重要な場面では、文字にしたり、口に出したりしないと、思っているだけでは気持ちは伝わりません。米国人はコミュニケーションのトレーニングも受けますし、サンキューカードやクリスマスカードなどお互いに気持ちを伝え合うメッセージカードが普及しています。多民族国家、様々な文化や宗教を持った多様な国民で成り立つ米国特有の教育や文化が背景にあるわけですが、たった一言の励ましは、患者にとっては心強いものです。
米国で入院した際には、ボランティアスタッフの励ましの声にも救われました。まだ高校生のボランティアスタッフが、見知らぬ東洋人に「何か困っていることはありませんか」と話しかけてくれたのです。日本ではとても考えられない光景です。がんは、医療スタッフや患者家族だけではなく、社会全体で支えていくべきものであると感じるとともに、米国におけるこうしたボラティア人材の層の厚さに驚きました。
標準治療に対する日米格差
――日米の違いは、文化だけではなく、医療そのものの違いへの驚きも著書で指摘されています。
とにかく、米国の医療は高いということに驚きました。日本人は健康保険証があれば、誰でもどこでも低コストで良い医療を受けることができます。それが米国では、手術で病院に行くとまず言われるのが、「アメックスのゴールドカードを持っていますか」であり、要は医療費が払えるかの確認です。それ相応のコストを支払っているから、質の高い医療はもちろん、病室は広いし、アメニティサービスも充実しているのです。支払い方法も驚きました。病院から請求書がくるのではなく、外科医や麻酔医など個人から個別に請求書がくるのが米国です。
米国では在院日数が短いことにも驚きました。あんなに高い入院費なら一日でも早く退院したいですよ。日本もDPC制度が普及してから在院日数はかなり短くなってきましたが、当時(1986年)は入院期間の半分が術前検査というような状況でした。食事も日本では全粥、七分粥、五分粥、三分粥ときめ細かいですが、米国は1日オートミールを食べたら、翌日から通常食というようなペースです。日本でも現在、患者の年齢や回復度に応じてもっと柔軟に対応できるようになりました。
ただ、米国以外の国の多くが皆保険制度を取り入れているので、医療の日米比較は難しいのではないでしょうか。
――医療の質についての日米比較はどうでしょうか。関原さんは最初の手術は米国で行い、その後の5回は日本で手術を受けられましたね。
大きく異なるのは、標準治療に対する姿勢です。米国は、明確かつ詳細な治療方法が定められており、その標準治療を厳守します。医療訴訟も多いですから、当然でしょう。しかし日本では、例えば標準治療における切除範囲より広く切った方がいいなどと、医師が独自に判断することもあり、医師の裁量権は米国とは少し違っています。
日本は、大腸がんなど消化器系の5年生存率は高いです。ただ、これをもって日本の医療の質が高いとは言い切れません。手術の難易度、過剰手術、食生活、や早期発見率などさまざまな要因が考えられるため、医療の質を比較するというのも、やはり難しいでしょう。
――医療の質のバラつき(病院間、医師同士の格差)という観点ではどうでしょう。
それは確実に米国の方が優れています。専門教育が確立し、標準治療が浸透しているからです。ただ、日本では手術して見て触って、その場で臨機応変に対応するということもあり、標準治療を厳守することだけがすべてではないという思いもあります。
米国は、専門医制度も優れています。特に、心臓外科など収益性の高いものは優れていると思います。収益性が高いから、厳しい競争を勝ち抜き、そこに優秀な人材が集まるという流れが確立されているのです。米国には学閥もなく、医師一人ひとりの評価も厳しくされる仕組みになっています。
一方、日本は米国ほどの競争がありません。大学病院系列でサラリーマン的に過ごす医師と、系列から飛び出し、トップレベルの技術と知識を持つ医師に師事したり、そういう医師が集まる組織に所属する医師とが混在しているため、また患者が自由に医師を選べるフリーアクセスが許されるために、患者にとって良い医師や病院の選択は本当に悩みます。
賢い患者は主体的な患者
――医療の質にバラつきがある日本では、病院探し、医師探しが患者にとっては非常に重要です。良い医師と出会う方法、正確な情報を入手するためのポイントは何でしょうか。
例えば、私の国立がんセンターの肝臓がんの主治医だった幕内雅敏先生(東大名誉教授:元日本赤十字社医療センター院長)や肺の執刀医土屋了介先生(元国立がんセンター院長)は、執刀いただいた当時は30歳代の一介の若手医師です。今でこそ世界的に知られる肝臓外科や呼吸器外科手術分野の権威ですが、正直、そんなことは誰も分からず、運が良かったとしか言いようがありません。
ただ、がんはチームで治療していくものなので、国立がんセンターのような然るべき施設では、人材もそろっていますし、情報もしっかりと共有されています。仮に経験の少ない若手が診察しても、その情報はベテランも交えたチームで治療方針を決定し、手術にも立会います。やはり、病院選びが重要なのではないでしょうか。そうはいっても、がん対策の進捗に伴い、がん医療の均てん化が推進されてきましたから、胃がんや大腸がんなどは、全国どこでも拠点病院間での治療に大きな差はなくなりつつあるとは思っています。
――転移を繰り返すなど厳しい状況の中で、悲観せず、前向きに正しい治療方法にアクセスしようとし続けた行動力や粘り強さには感服いたしました。自らの行動力や粘り強さを支えていたものは何なのでしょうか。
今はがんに限らない医療情報が、インターネットを中心に溢れかえっており、いかに正しい情報を見極めるかが重要になってきています。とはいえ、がんはがん患者一人ひとりで症状が異なるため、主治医が言うことをしっかりと聞き、正しく理解できる知性がなければ、いくら情報を集めても意味がありません。ですから、主治医との信頼関係を構築することが、今も昔も、正しい治療をするためには最も重要なことなのです。
どんな医師だって、しっかりと聞くべきことを聞けば、答えてくれます。そのためには己の病状を正しく理解しておくことが前提です。それを主治医からしっかりと聞かなかったり、誰かに言われたことを鵜呑みにしてトンチンカンなことを聞いてみたり、自分の言いたいことばかり言っているようでは、主治医との会話が成り立たず、いつまで経っても正しい治療方法にたどり着けず、賢い患者になることはできません。たった一つの命なのですから、患者はもっと主体的に自らの病に向き合い、考え、行動することが欠かせないのです。その心構えが最も重要です。
もう一つはがん医療が進歩したとは言え、患者の4割は命を失う厳しい病であることは厳然たる事実です。がんを患うと、すべて一期一会、いつ死が訪れても受容れられるよう、今やりたいことはすべて実行するという物事を先送りせず、日々精一杯生きることが凝縮した人生となり、己を逞しくすることに繋がると思います。
連載◆「プロ患者」に聞く正しいがん治療
(1)主治医との信頼関係なくして、最善の医療なし
(2)がん診療拠点病院、各都道府県に一つで十分