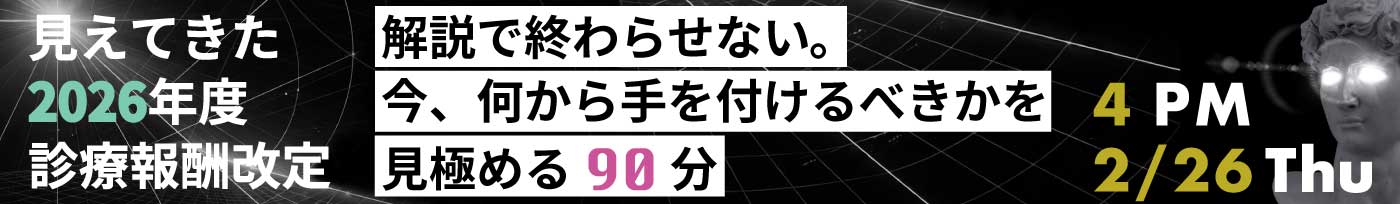「全員主役」が一変させた院内外の好循環――がん症例13倍のチーム医療(2)
2018.5.18.(金)
7年で乳がん症例が13倍以上に急成長した湘南記念病院(神奈川県鎌倉市、161床)。急成長の背景には、「患者を支える」という医療の本来的な目的を貫くため、これまでの常識にとらわれない「全員主役のチーム医療」の推進がありました。
理想の実現をスタートできた2つの出会い
当時、コロンビア大学メディカルセンターの乳腺外科部長だったフレヤ・シュナベル氏(現ニューヨーク大学ランゴーンメディカルセンター乳腺外科教授)から「支える医療」のあり方を学び、帰国した湘南記念病院の乳がんセンター長である土井卓子氏。ただ、学んだ「支える医療」は、その考え方はもちろん、人員体制、さまざまなツール、そのほとんどが当時の職場で受入れられることはありませんでした(「支える医療」と同じ考え方に立つ患者支援サービス「キャンサーナビゲーション」に関する記事一覧はこちら)。
「支える医療」を行うためには、非医療職のがん体験者、ピアサポーター(同じ患者の立場にある患者支援者)の存在が欠かせません。しかし、ピアサポーターを受け入れることは、当時の日本の医療機関における人事制度や診療報酬を考慮したとき、そもそも関係者の理解を得ることすら、かなり難しいことだったのです(関連記事『病院にピアサポーターが必要な本当の理由、がん患者を支える非医療職の実像』)。
途方に暮れた土井氏の前に現れたのが、乳がん患者の紹介元の一つ、湘南記念病院の井上俊夫院長。「支える医療」などについて意見交換をする中で、「乳がんセンターの開設を考えています。一緒にやりませんか」と井上氏が切り出しました。当時、土井氏は500床台の国立病院の部長職。100床台の民間病院への転身を「都落ち」と揶揄する声もありましたが、「支える医療をやれるのなら」と新天地で理想の医療を追求することを決意します。

湘南記念病院の井上俊夫院長(湘南記念病院のホームページより)
その頃、もう一つの出会いがありました。「支える医療」の必要性を講演会などで訴えていた土井氏に、がん患者支援団体のキャンサーネットジャパンの関係者が声をかけます。
「『乳がん体験者コーディネーター(BEC)』の講師になっていただけませんか」
BECは、乳がんに対する正しい知識を身に着け、正しい情報にアクセスして問題解決に導く力を身に着けるための養成講座。BECの資格を持つピアサポーターも多いのです。この提案に土井氏は「願ったり叶ったり」であると二つ返事で承諾。BECの講師を通じて紹介されたのが、乳がんセンターの立ち上げの時から、土井氏と一緒に「支える医療」を展開していくことになるBEC2期生の山口ひとみ氏です。

湘南記念病院の乳がんセンター立ち上げ当初からピアサポーターとして活躍する山口ひとみ氏(右)と土井氏。
ようやく「支える医療」を行う場所と必要な人材を手に入れた土井氏。理想の実現に向けたスタートを切れたはずでしたが、土井氏は当時のことを振り返ります。
「患者は集まらず、院内の理解も得られない。そんな状況の中で、山口さんと二人でずっと、空回りしているような日々が続きました」
3―4年続いた空回りの毎日
問題は大きく2つありました。
1つは、院内の理解です。院長の後ろ盾を得てはいたものの、「支える医療」に対する院内の理解は、なかなか進みませんでした。
「どうして患者にお菓子など出すのか」
「なぜ、乳がんセンターだけ特別扱いなのか」
土井氏は都度、▽がん患者はサバイバー期間も含めると命をお預かりする期間が長い特殊な疾病であること▽医師と患者のコミュニケーションエラーで標準治療からのドロップアウトを防ぐため、どうしてもピアサポーターのような存在が必要であること▽冷静さを取り戻して帰宅してもらうためには、温かいお茶と甘いお菓子が必要であること――など、さまざまな院内からの反発にも粘り強く回答していきました。
それでも当初は院内の理解はなかなか得られず、ウォーターサーバーやお菓子などは土井氏が自腹で購入するというような状況でした。
2つ目の問題は、山口氏の存在です。患者のさまざまな相談を受ける山口氏のようなピアサポーターと看護師の役割分担をどうすればいいのか、ピアサポーターとどう接したらいいのか――などの戸惑いが院内に生じるのは、当然だったかもしれません。
看護師とピアサポーターの間に生じている大きな溝――。土井氏は、この溝をどう埋めればいいか頭を悩ませていましたが、3―4年の時を経て、この溝は徐々に埋っていきます。
「この期間、山口さんはかなり悩んでいたと思います。それでもお昼時間に看護師たちの輪に入っていくなど、粘り強く看護師たちの理解を得ようと努力し続けました。やがて、看護師たちもその思いに答えようと歩み寄り始め、一種の共同戦線のようなものができあがりました。そこから一気に、ピアサポーターも含めたチーム医療が展開していきました」(土井氏)
スタッフ本来の力が手繰り寄せた好循環
湘南記念病院の乳がんセンターは今、職種ごとに役割が明確に分かれています。しかも、医師に仕事の量が偏ることなく、どの職種も等しく重要な役割を担っています。

乳がんセンタースタッフの一部。マンモグラフィサンデーの時にそろいのピンクリボンシャツで。
例えば、がんの告知にショックを受けた患者。必要な説明の途中で部屋を出ていってしまった患者を看護師が追いかて落ち着かせ、改めて必要な説明を行ったところで、ピアサポーターにバトンタッチ。診察室への入室を促し、次回の診察予約を入れる――。このような連携プレーが、医師の関与がほとんどない状況で行われています。これについて土井氏は、「乳がんセンターのスタッフ全員に、『間違ったことを言ってしまってもいいので、業務の一部を任せます』と宣言してあります」と説明します。これは医行為(医師免許がなければできない業務)を多職種へ移管することではありません。何でもかんでも医師が指示のではなく、すべてのスタッフが主体的に動くことで、「全員が主役のチーム医療の実現を目指しています」(土井氏)。
そのため、そのほかの職種でも、抗がん剤治療方針の決定に欠かせない薬剤師、画像診断に欠かせない放射線技師など、すべてのスタッフが主体的に活躍しています。「思い切って任せると、すべてのスタッフがものすごい力を発揮します。医師が否定するから動かない、医師が認めないからやる気を失っていく――。そうやって本来あった仕事への熱意を削がれ、本当の力を発揮できないでいる医療従事者は、少なくないのではないでしょうか」(土井氏)。
全員が主役のスタッフたちの意識は、患者家族や院外にまで伝播していきます。
手作りの小さなぬいぐるみ「いたくない象くん」は、患者を支える名物アイテムです。当初は、抗がん剤治療を受ける母親のために、小学校3年生の女の子が作ったものでした。母が「いたくない象くん」を握りしめて苦しい治療に絶えた姿をみたこの子は、その後、毎月、「いたくない象くん」を何体か作り、乳がんセンターに置いていくようになりました。「薬の飲み忘れを防ぐための手作りケース、抗がん剤治療の際に使ったニット帽を置いていく完治した患者など、さまざまなものがセンターに置かれていきます。『自分たちができることは何だろう』と、乳がん治療にかかわる多くの人たちが主体的に動いてくれた結果ではないでしょうか」(土井氏)。

握りごごちがよく、安心できると評判の「いたくない象くん」
この勢いは、外部にも伝播していきます。患者や家族の評判が次々と患者を引き寄せ、その評判は同じ乳がんを専門とする医療従事者たちの聞き及ぶところになります。国内有数のがん専門病院から井上謙一医師が、日本ではまだ少ない腫瘍内科医の堤千寿子医師が合流するなど、スタッフは徐々に増えていき、現在、医師は7人。看護師などそのほかの職種も、噂を聞きつけては「『支える医療』をやりたい」と乳がんセンターに集ってきました。

「『支える医療』をやりたい」と医療従事者が集まり、2018年4月時点で医師は7人(湘南記念病院のホームページより)
主体的に全職種が主役となるチーム医療が、「支える医療」の推進を担い、それが患者と患者家族に受入れられ、それが院外にも伝わって医療従事者が集まる。人が増えるから、さらに「支える医療」を強化できる――。この好循環が、7年で症例数13倍以上という急成長を大きくけん引していきました。
直感で考えれば当たり前のこと
湘南記念病院の乳がんセンターの好循環は、チーム一丸となって「支える医療」を実践するという土井氏の決断が起点になっていると言えます。チーム医療の必要性が指摘され、ブレストケアナース(乳がん看護認定看護師)や特定行為研修制度など、資格や制度は整備されつつありますが、それらが十分に普及しているとは必ずしも言いづらい状況が続いています。土井氏はなぜ、このような取り組みを実践できたのでしょうか。
「1つは、単純に多忙で手が回らず、任せざるを得なかったということです(笑)。ただ、任せてみると、さまざまな職種が異様な力を発揮し、嬉々として自分たちで考え、自分の頭で判断し、予想を超えた働きができるようになっていきました。
それと、普通に一人の人間として考えたら、当たり前のことだということです。若手の駆け出しの外科医だった頃、まだまだ乳がんはメジャーな疾病ではなく、女性ならではの悩みを男性の医師に話せず、気づいてももらえず、院内で一人泣いている患者さんを、何人も見てきました。『支える医療』をやりたいと思ったのは、その時に医師としてではなく、一人の同じ女性として『この人たちを何とかしてあげたい』と強く思ったことが、思えば最初のきっかけです。
ですから、普通に一人の人間として直感で考えてみてください。認められ、任され、必要とされれば、誰でもその期待に答えようと頑張り、本来の力を発揮できるはずですよね。直感で考えれば、多職種が主体的に活躍できないチーム医療なんて、あり得ないんです」
連載◆がん症例13倍のチーム医療
(1)大学病院レベルの集患力、「支える医療」とは
(2)「全員主役」が一変させた院内外の好循環
(3)患者に寄り添う傾聴に最も大切なこと