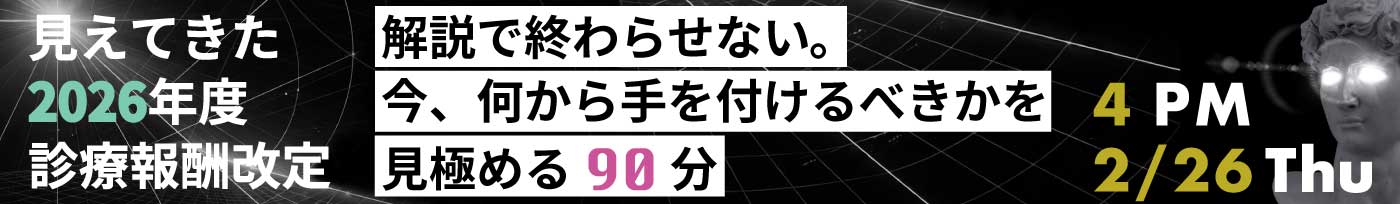子どもの医療費負担を軽減する助成制度、継続すべきか見直すべきか―子ども医療制度検討会
2016.2.25.(木)
子どもの医療費について、市町村が行っている助成制度をどう考えるべきか、助成を行う場合に市町村国保に投入される国費が減額されるが、それをどう考えるべきか―。こういった議論が、厚生労働省の「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」で進められています。
助成制度については「少子化対策の重要な一施策である」として継続を求める意見がある一方で、「過剰受診を招いている可能性もある」と批判する声も出ています。
検討会では今夏(2016年夏)にかけて意見をまとめる予定で、その中で「制度改正が必要」という結論が導かれた場合には、社会保障審議会・医療保険部会で具体的な議論が行われることになります。
医療保険制度では、かかった医療費の9-7割を保険者(健康保険組合や国保など)が給付し、残りの1-3割を患者自身が医療機関の窓口で負担しています(一部負担)。この一部負担の割合は、原則として▽小学校入学前までは2割▽小学校入学以降70歳になるまでは3割▽70-74歳は2割(段階的に3割に引き上げ)▽75歳以上は1割―に設定されています。
ただし、子どもの医療費については市町村が独自の判断でさまざまな助成を行っており、小学校入学前までは2割負担分を全額市町村が負担、つまり「自己負担ゼロ(無料)」としている市町村も少なくありません。
これは、子どもを持つ親にとっては有益な仕組みで、「少子化対策にとって重要」と評価する声が数多くあります。
その一方、一般に「医療費の自己負担が減った場合、医療機関にかかる人が増え、自己負担減額分を超えて医療費が増加(波及増)する」ことが知られています(長瀬効果と呼ばれます)。国は、この波及増分は「市町村が負担するべき」と考え、市町村が子どもの医療費に対する助成を行う場合、市町村国保に対する国庫負担を減額しているのです(減額調整制度)。例えば、「子どもの医療費を無料」にした場合には国庫は86.11%に、1割に減額した場合には93.49%に国庫負担が減額されます。
この減額調整制度について、市町村や都道府県からは「少子化対策という国の大方針と逆行する」として廃止を求める意見が出されています。
検討会では、昨年(2015年)9月から、こうした状況のほか、小児に対する医療提供体制や小児医療の診療報酬などを総合的に議論し「子どもに対する医療制度の方向性」を探っているのです。
25日に開かれた会合では、これまで委員から出された議論を整理した資料が厚労省から提示されました。論点は多数ありますが、(1)子どもの医療費を助成する仕組みをどう考えるべきか(2)市町村が医療費助成を行った場合に、国庫負担を減額する仕組みをどう考えるか―の2点が大きなポイントと言えます。
(1)の医療費助成については、「重要な少子化対策である」という意見がある一方で、「国が一定の線を引くべきでないか」「過剰受診を招く可能性があり好ましくない」という指摘もあります。
25日の会合では、釡萢敏構成員(日本医師会常任理事)が「子ども医療費助成で,いわゆる『コンビニ受診』のような不適切な受診は生じていない。継続すべきである」と主張。また、阿真京子構成員(知ろう小児医療守ろう子どもたちの会代表)も「いざというときに躊躇なく医療機関にかかれる仕組みは非常に重要である」とし制度の維持を強く要望しています。
これに対し、小黒一正構成員(法政大学経済学部教授)は「国と自治体の関係者が集まり、大きな方向性を検討するべき」との見解を述べています。現在は、自治体が独自の判断で助成を行っていますが、「少なくとも未就学児については、どこに住んでいても同じ仕組み」であるべきとの考えに基づく意見です。
ただし、そこで「全国一律に無料」とする考えに、小野崎耕平構成員(日本医療政策機構理事)が懸念を示しています。小野崎構成員は「現在のフリーアクセス、多くの自治体で導入される無料化といった仕組みは素晴らしい」と評価した上で、「一度無料化してしまえば、後に有料化することは極めて困難である。『子ども医療費の無料化』の目的がどこにあるのか、目的を明確にした上で慎重に議論する必要がある」と指摘しています。
なお、「低所得者」など、真に支援が必要な人に限って負担割合を引き下げるべきとの指摘も出ています。
ちなみに、厚労省保険局調査課の秋田倫秀課長は「子どもの患者負担を無料化」(医療保険の仕組みとして、●歳までは無料とする)した場合に、医療費にどのような影響が出るのかを「粗い試算」として提示しています。
それによると、高校卒業まで無料化した場合に給付費(医療保険から支払われる費用)は8400億円(患者自己負担減少分が5300億円、波及増分が3000億円)、中学卒業まで無料化した場合に給付費は7100億円(患者自己負担減少分が4700億円、波及増分が2400億円)増えることなどが分かりました。もっとも、仮定(すでに未就学児にはすべての市小村で無料化行われている、など)を置いた数字である点には注意が必要です。
もう一つの大きな論点が、「医療費助成を行った場合の、市町村国保への国庫負担減額調整」をどう考えるかという問題です。
これについては、「自治体が単独で減免することに伴う医療費増は、広く国民全体が負担するのではなく、その自治体が負担するという考え方は適切である」とする意見がある一方で、「減額調整がなくなれば、その分の国費を他の少子化対策に充てることもでき、より少子化対策が充実する」(宮澤誠也構成員:新潟県聖籠町保健福祉課長)という指摘もあります。
なお、この減額調整は現物給付として行った(つまり、患者の窓口負担を直接減額・無料化する)場合には発動されますが、償還方式で行った(患者は2割の窓口負担を支払い、後に市町村に現金の還付を求める)場合には発動されません。こうした点についても、今後、検討が行われる可能性があります。
ところで、医療費助成によって医療費にはどの程度の波及増があるのでしょう。助成制度を拡充した10の自治体(減額調整額が10%以上増加、人口20万人以上)について調べたところ、「助成制度の拡充が大きい(減額調整額の増加幅が大きい)ほど、医療費の伸びも大きい」ことが分かりました。
例えば「償還方式から現物給付方式に変更」(自己負担は無料)した自治体では、同じ県の他自治体に比べて医療費全体の伸びが6%超大きくなっています。
一方、同じく「償還方式から現物給付方式に変更」した別の自治体では、自己負担の割合を増加したため、医療費全体の伸びは同じ県の他自治体よりもわずかに下回っています。秋田調査課長は「『償還方式から現物給付方式への変更』と『自己負担割合の増加』で相殺となった可能性がある」とコメントしています。
【関連記事】
2016年度診療報酬改定、実は「小児医療の見直し」が大きなポイント―中医協総会
かかりつけ医以外の外来受診、新たな定額負担の是非について年内に結論を出す―社保審・医療保険部会