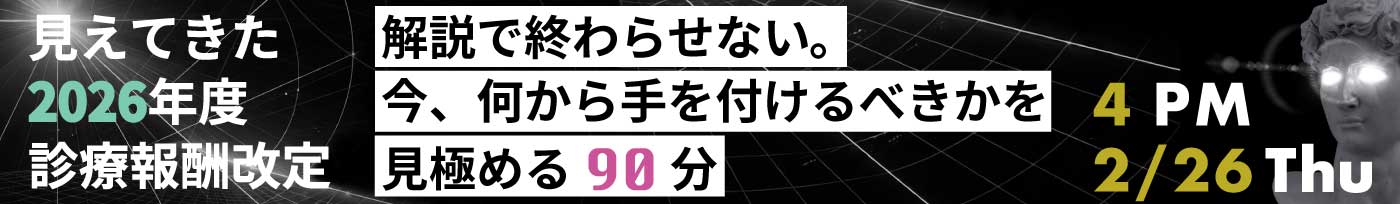機能分化と在院日数短縮で病院の合併統合進む、重要なのは「キーマンの設定」―GHCが「地域医療構想とその先にあるもの」をテーマにセミナー開催
2015.5.25.(月)
病院の合併統合にあたって、最も重要なポイントは「誰をキーマンに据えるか」「統合の相手方へ敬意を払えるか」である―。県立病院と市立病院という、異なる設立母体を持つ自治体病院同士の合併を見事成功させ、厳しかった経営状況をV字回復させた日本海総合病院の栗谷義樹理事長が、GHCが23日に開催したセミナー「『地域医療構想』とその先にあるものとは」で強調しました。
また厚生労働省保険局医療介護連携政策課の渡辺由美子課長は、「これからの病院経営は、個々の病院という『点』の視点から、地域という『面』の視点へと意識転換しなければならない」と述べ、「2025年に向けて国や地域で構築進めている地域包括ケアシステムの中では、病院も重要な役割を担う。急性期病院であっても介護保険制度への関心を高めてほしい」と強調しています。
日本海総合病院は、旧山形県立日本海病院と旧酒田市立酒田病院が合併統合して08年4月に発足しました。現在は、独立行政法人「山形県・酒田市病院機構」として、旧日本海病院が急性期に特化した「日本海総合病院」に、旧酒田病院が回復期・慢性期を中心に担う「酒田医療センター」に機能分化しています。
「自治体病院同士が合併した成功事例」として名高く、メディ・ウォッチでも今年2月に、同機構の理事長でもある、日本海総合病院の栗谷義樹院長をインタビューしました(「合併後に自分の居場所がなくてもよい」キーマンがそう思えるか否かが合併の鍵-日本海総合病院)。
23日のセミナーで栗谷院長は、病院の合併統合を成功させる最大のポイントとして「誰をキーマンに据えるか」を掲げました。
日本海総合病院のケースでは、山形県の齋藤弘知事(当時)と山形大学の嘉山孝正医学部長(当時)、さらに栗谷院長の三氏でしょう。栗谷院長は「役者がきちんとそろっていなければ合併統合は成功しない」と強調します。
また、「合併相手に最大限の敬意を払う」ことも極めて重要です。栗谷院長は「2つの組織が一緒になったとき、片方が出て行ったのでは単なる吸収で、真の合併ではない」と指摘。日本海総合病院では、同じ診療科に旧日本海病院と旧酒田病院のスタッフが混在するため、合併当初は人事や診療内容などさまざまな点でトラブルが生じたと予想されます。その際、一方に肩入れすれば、眼に見えない亀裂が入り、やがては組織の崩壊につながりかねません。そのため栗谷院長は、「山形大や東北大の医学部長にも加わってもらい、職員の能力・実績を公正公平に評価し人事を決めた。また、両大の教授にエビデンスを出してもらい、診療内容面での懸念を一つ一つ解消していった」と振り返ります。
合併による効果は着実に表れています。統合前の07年度には、141億円7100万円の収益に対し、支出が153億4900万円だったため1178億円の赤字決算でした。これが合併直後の08年度には、ベッド数・職員数共に縮小されにもかかわらず、141億9300万円の収益を確保する一方、支出が143億1700万円に減少したため、赤字は12億円に圧縮。さらに直近の14年度では、収入は176億5000万円に増加し、支出は173億6900万円で、2億8100万円の黒字決算となっています。
この背景には、▽医師数の増加▽診療圏が増加し、ほかの地域からの新規入院患者数の増加▽手術件数の増加(地域でのシェアが合併後にトップとなった)▽1日当たり単価の上昇―などさまざまな要素が絡んでいますが、栗谷院長が特に重視するのは「地域医療・介護連携」のようです。
日本海総合病院では、地域の病院と連携した「ちょうかいネット」を構築し、処方、注射、患者バイタルといった診療録のすべてを共有しています。密な情報連携によって紹介元、逆紹介先の病院、診療所、介護施設との関係が円滑になるだけでなく、同病院から診療所などへ患者を逆紹介する際に、ネットワークの情報を活用すれば済み、医師が別に詳細な情報提供をする必要がなくなったため、大幅な勤務医の負担軽減が図られています。
「財務の好転による機器の充実や、負担軽減によって優秀な医師が集まる」→「医療の質が高まり患者が集まる」→「更に財務が好転する」という好循環が形成されていると言えるでしょう。
厚労省は、医療・介護のシームレスな連携を重視し、14年7月に保険局に「医療介護連携政策課」を新設しました。その初代課長に就任したのが、渡辺課長です。
渡辺課長は冒頭、「これからの病院経営においては『点』から『面』への視点の転換が必要である」と指摘しました。
地域医療構想に沿って地域(主に二次医療圏)での機能分化が推進される中、医療機関にとっては、ほかの医療機関や介護施設との連携が不可欠です。渡辺課長は、「これからは地域全体の医療ニースを把握し、その上で自病院の地域での立ち位置を確認しながら病院を運営していかなければならない」と強調しました。
また、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる25年に向けて、国と自治体では「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。渡辺課長は「地域包括ケアシステムというと、介護や在宅医療の側面だけが注目されがちだが、急変時の受け入れなどを含め、急性期病院も重要な一員である」とし、診療所や介護施設はもとより、ほかの生活支援サービスなどとの連携にも関心を持ってほしいと要望しました。
特に高齢化の伸展に伴って、認知症高齢者数も増加することから、「認知症高齢者の身体合併症」への対応も重要になってきます。その際、急性期病院のスタッフが、認知症患者への適切な対応方法を知らなければ治療にも支障が出てきてしまいます。
さらに渡辺課長が強調したのは、「今後は治すだけでなく、『支える』医療が重要になる」という点です。これに関連して、15年度の介護報酬改定では「口から食べる楽しみの支援の充実」(口腔・栄養管理の評価充実)が行われました。摂食・嚥下機能が低下した高齢者でも、「口から食べる楽しみ」を得られるよう、多職種が連携して支援することを介護報酬で高く評価するもので、渡辺課長はこれを「支える医療の1つのメッセージと言えるのではないか」と説明しています。
GHC社長の渡辺幸子は、日本はOECD(経済協力開発機構)の中で最も急性期病床が多く平均在院日数が長いと示した上で、2025年に向かって高齢化が進むことで医療需要は増大するものの、多くの地域ではそれを上回るスピードで急性期病床の在院日数短縮と外来医療へのシフトが進むため、延べ入院患者数は今後も減少することを指摘。「急性期に特化するなら、ダウンサイジングを行うのか、それとも、急性期以外の地域包括や療養への機能分化を進めるのかを早急に検討し判断しなければいけない」と強調しました。
地域医療構想が進む中、この判断が遅くなれば、地域での居場所がなくなることすら予想されるからです。
さらに、GHCが相澤病院と共同研究を行ったところ、同病院では「急性期としての必要病床数は502床(当時)のうち将来的には、わずか255床にとどまる」という衝撃的な数字が出たことも紹介しました。同病院では、将来をにらんで病床の再編を進めています。
また、院内の機能分化を既に進め、病院の分割を行った佐久総合病院の事例も紹介。同病院では、回復期を増床した本院と、急性期に特化した佐久医療センターに機能を分化し、最適な医療提供体制の構築を目指しています。
このように機能分化が進む中では、「連携」が必須となります。さらに1入院当たりの包括支払いシステムであるDRG/PPSが導入されている米国では、連携の先を行く「統合」が進み、病院や介護施設の間でIDS(integrated delivery system)が構築されています。
渡辺はIDSの構築によって、▽規模の経済(資本、人、情報)▽クリニカルインテグレーション▽より広い地域からの集患▽共同購買▽保険者への対抗力向上―という価値を見込めることを紹介。日本でも近い将来、IDSの構築を進める必要が出てくると見通しました。
【関連記事】