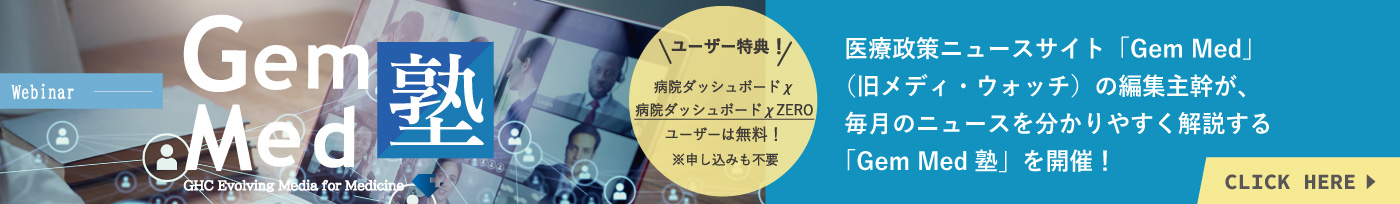大腸がんの在院日数、短縮傾向もなお病院格差-CQI研究会が経年分析
2015.7.27.(月)
がん専門病院で腹腔鏡手術や開腹手術を受けた大腸がん患者の入院期間が、2011年から14年にかけていずれも短縮傾向にあることが、CQI(Cancer Quality Initiative)研究会の調べで明らかになりました。手術を受けてから退院するまでの術後日数にも短縮傾向が認められました。ただ、これらの日数には、依然として病院によって大きな差があることも分かりました。
 CQI研究会は、全国のがん専門病院の有志らが07年に立ち上げ、DPCデータを使って参加病院のがんの診療プロセスを分析したり、臨床指標を分析したりして、実名で結果を発表しています。データ分析は発足当初からGHCが担当しています。11回目となる今回は、がん診療連携拠点病院など計106病院が分析に参加し、大腸がんや肺がん、乳がんのデータを比較、分析結果は25日に東京都内で開かれた例会で発表しました。参加病院が100を超えたのは今回が初めてです。
CQI研究会は、全国のがん専門病院の有志らが07年に立ち上げ、DPCデータを使って参加病院のがんの診療プロセスを分析したり、臨床指標を分析したりして、実名で結果を発表しています。データ分析は発足当初からGHCが担当しています。11回目となる今回は、がん診療連携拠点病院など計106病院が分析に参加し、大腸がんや肺がん、乳がんのデータを比較、分析結果は25日に東京都内で開かれた例会で発表しました。参加病院が100を超えたのは今回が初めてです。
大腸がんでは、106病院によるデータ分析のほかに、11年に実施した7回目と14年に実施した今回の分析の両方に参加した51病院を対象に、在院日数などの指標がどれだけ変化しているかも分析しました。いずれの年も7-12月に退院した症例をピックアップ。在院日数や術後日数のほか、抗生剤の投与期間などでも経年変化を追いました。
分析結果によりますと、腹腔鏡手術を受けた症例の在院日数は、11年が平均16.4日(中央値は14.0日)だったのに対し、14年には15.2日(13.0日)とこの4年間で1.2日短縮したことが分かりました。開腹手術を受けた症例では、11年が平均23.7日(20.5日)、14年が19.1日(17.0日)でした。開腹での短縮幅が腹腔鏡を大きく上回りましたが、14年現在、両者には依然として4日近い開きがあります。


また、14年の平均在院日数を病院間で比較すると、腹腔鏡の場合は20日を超えていた病院が3か所ありました。これに対し、最短の病院は7日程度でした。開腹での最短は13日前後でしたが、中には40日を超える病院もありました。
これに対して術後日数の平均は、腹腔鏡では11年が11.8日(中央値10.0日)、14年が10.6日(9.0日)で1.2日程度短縮。これに対して開腹では17.6日(14.0日)から13.2日(11.0日)に短縮していました。14年現在の術後日数は、腹腔鏡の場合は最短が5日程度でしたが、最長の病院では16日程度に及びました。開腹の場合にも格差が認められ、最短の病院では10日を切ったのに対し、中には35日近い病院もありました。
一方、抗生剤(注射)の平均投与期間は、腹腔鏡では11年の2.6日(中央値2.5日)から14年には2.3日(2.0日)まで短縮。これに対して開腹では3.4日(3.0日)から2.7日(2.0日)という結果で、11年に0.8日あった腹腔鏡との格差は、14年には0.4日にまで解消しました。
一連の分析結果を25日の例会で発表した岩手県立中央病院の望月泉院長は、「平均在院日数や術後日数はいずれも短縮する傾向だが、中には4年前に比べて長くなっている病院もある」と述べ、自病院の現状を確認するよう呼び掛けました。
一方、肺がんの分析は、106病院で手術を受けて14年7-12月に退院した計2万6467を分析対象にしました。分析結果によりますと、全症例の9割近くに胸腔鏡手術で対応している病院が過半数を占めましたが、8割近くに開胸手術を行っている病院もありました。
肺がんの症例の在院日数は、胸腔鏡が平均12.2日(11.0日)、開胸が14.0日(13.0日)でした。これに対して術後日数は、胸腔鏡が平均8.6日(中央値8.0日)、開胸が平均10.3日(9.0日)という結果。胸腔鏡では過半数の病院が術後日数を平均10日以内に抑えていましたが、開胸では15日を超える病院も目立ちました。
これらの病院では年換算症例数が少なく、分析結果を発表した神奈川県立がんセンターの中山治彦副院長は、「何らかの大きな開胸手術をたまたま実施して、長引いてしまったのではないか」との見方を示しました。
抗生剤の投与期間は、胸腔鏡が平均2.0日(中央値も同じ)、開胸でも2.2日(中央値2.0)日と大差はありませんでした。国立がん研究センターのクリティカル・パスでは術後1日目までの投与を推奨していますが、4日目以降も投与するケースも見られました。抗生剤の種類では、胸腔鏡か開胸かによらず、国立がん研究センターが推奨する第1世代セフェム系の使用割合が圧倒的に高いことが分かりました。
乳がんでは、乳房温存術の実施状況などの臨床指標について、乳がん関連の診療ガイドラインの順守状況を把握しました。乳房温存術については、各病院へのアンケート調査をベースに、14年4月-15年3月に診断を受けたか、手術を実施した症例を対象に実施状況を分析しました。
ステージI-IIの浸潤性乳がんのうち、腫瘍径が3センチ以下で広範囲にわたる進展や多発がんがない場合、ガイドラインでは乳房温存術を実施したり、こうした術式があると患者に説明したりすることを推奨しています。しかし、アンケートに回答した31病院のうち、こうした患者すべてに乳房温存術を実施していたのは11病院と、半数に届きませんでした。温存術が推奨される全症例ベースでの実施率は74.4%でした。
また、腋下リンパ節への転移が陽性で、手術を受けたすべての患者にリンパ節郭清を実施していたのは31病院のうち11病院、症例ベースでの実施率は70.5%でした。
国内のガイドラインでは、こうした症例にはリンパ節郭清を実施するよう強く奨めていますが、岩手県立中央病院の宇佐美伸・乳腺外科医長は、「すべての症例に実施する必要があるのかどうか、腫れている所だけでいいのではないかなど、(解釈が)混とんとしている」との見方を示しました。

今回の例会では、米国のクイーンズメディカルセンター(ハワイ州ホノルル)のポール・モーリス・外科部長兼がん委員会議長が特別講演し、同センターによる医療の質改善の取り組みを紹介しました。
クイーンズメディカルセンターは、1859年に設立された非営利の病院です。モーリス氏によりますと、同センターは、かつては米国内では標準的な病院の1つにすぎませんでしたが、米国外科学会(ACoS)がん委員会で優秀施設に認定されるなど、現在では全米でも有数ながん専門病院としての地域を確立しました。
モーリス氏は、病院全体だけでなく医師の成績向上を後押ししたことが質の改善につながったと話しました。同センターの医師の成績を、ACoSのほか、米国国立がん研究所地域がんセンターなどさまざまなデータベースを活用して、プロセス指標やアウトカム指標を全米規模で比較し、これらの結果をベースに改善策を探ったということです。
モーリス氏は、医療の質を向上させるには、病院全体だけでなく医師の成績もベンチマーク分析する必要があると指摘しました。「多くの医師は自分自身が優れた仕事をしていると思いがちだが、実際に優れているかどうかは、エビデンスに基づいて初めて明らかになる」と述べました。
米国外科学会の手術の質向上プログラム(NSQIP)のデータベースでは、入院患者の重症度などのリスクを調整した術後30日目の死亡率や、術後創傷、脳卒中の発症率をベンチマーク分析し、現在では全米の水準に比べ同センターは軒並み良好だということです。
モーリス氏は、「外科医がこうした改善に取り組むことで、病院への医療費の償還が大幅に改善」すると述べ、感染症の予防などの取り組みが病院経営にも直結すると指摘しました。
【関連記事】
がん医療の臨床指標を定め、自院と他院のベンチマークすることで医療の質が向上
乳がんの治療法、放射線実施率など格差鮮明―CQI研究会、臨床指標20項目を調査
前立腺がん手術、在院日数最短はダヴィンチ、合併症発生率は?―第10回CQI研究会
CQI研究会とは
【関連記事】