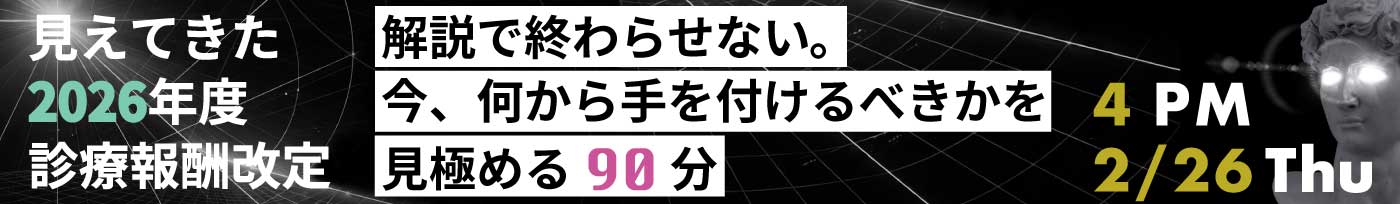経営者の信念とデータが正しい医療を創造していく―相澤院長がGHCセミナーで講演
2016.9.23.(金)
グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)は17日、都内で病院経営者向けセミナー「2018年を生き残る急性期病院、カリスマ経営者が選んだ2つの道 ~『急性期一本』を貫くか、『機能分化』に踏み切るか~」を開催しました。急性期病院向けに2回連続で開催するセミナー構成で、7月に「急性期一本」をテーマに前編、今回は「機能分化」をテーマに開催する後編という位置付けです(関連記事『済生会福岡総合の岡留院長、急性期一本で行くためには医療・介護連携体制の構築が不可欠』)。
この日は、数々の先進的な取り組みを行う相澤病院(長野県松本市)の理事長・院長兼最高経営責任者である相澤孝夫氏がメインスピーカーとして登壇。徹底したデータ分析をベースにたどり着いた「相澤東病院」の新設について、その経緯を振り返りました。そこには、経営と医療の質向上のため、自らが先頭に立ち、正しい医療を創造していこうとする信念が貫かれていました。
総入院期間76日短縮の衝撃
4年前の2012年、相澤病院とGHCは共同で、データ分析を通じて「急性期とは何か」を探る研究論文「入院期間(在院日数)からみる急性期医療必要度」をまとめました。急性期疾患ごとの医療資源投入量のデータを詳細に見ていくことで、「患者の状態が安定するまでの本来の急性期の期間は何日までなのか」を探るという内容です。その分析結果をベースに、当時、502床のうち7対1病床が468床あった相澤病院の「本来の急性期病床数」をシミュレーションすると、わずか225床であることが分かりました。その結果に、相澤院長は「衝撃を受けた」と振り返ります。
急性期病院が機能分化を検討する上でまず欠かせないのが、「急性期とは何か」という考え方をしっかりと押さえることです。増えすぎてしまった急性期病床の削減に国が乗り出し、「急性期らしさ」を一般急性期病院に求めている現状において、この点をシビアに考えることは欠かせません。
その一方で相澤院長は、回復期リハビリテーション病棟開設前後の、入院期間のデータにも着目します。具体的には、回復期経由で自宅退院した脳卒中の患者について。まず、回リハ病棟開設前は30.8日を自院の7対1病床で過ごし、その後、他院の回リハ病棟で106.1日過ごしていたので、入院してから自宅に戻るまで136.9日かかっていたことになります。それが回リハ病棟を開設した後、早期リハの多介入などで7対1病床の入院日数は13.7日に短縮(17.1日減)、自病院の回リハ病棟の入院日数は46.8日へ短縮(59.3日減)することに成功し、在宅復帰まで合計76.4日もの在院日数短縮につながっていることが分かりました。
大腿骨頸部骨折においても、回リハ開設前に合計101.2日だった在院日数が合計32.1日へ短縮(69.1日減)。相澤院長は改めて「急性期とは何か」という考えを深めつつ、まずは急性期病床からの早期退院を目指し、医療連携センターと退院支援室を強化。その一方、周囲に急性期を脱した患者を受け入れられる病院の数にも限りがあるため、16年2月に相澤東病院(地域包括ケア病棟42床)の新設に至りました。
現時点では、収益面で考えると課題もあるようです。ただ、「急性期とは何か」を医療資源投入量で判断する方法や、急性期病床からの早期退院を促す退院支援システムなどは、「高度急性期」の定義や退院支援加算のように、国が後追いで制度化の参考にしたと見られる取り組みだったと言えます(関連記事『高度急性期は3000点、急性期は600点、回復期は225点以上と厚労省が提案』『専従の退院支援職員配置など評価する「退院支援加算1」、一般600点、療養1200点』)。
こうした取り組みは、徹底したデータ分析と医療の質向上の観点から、「これがこの地域における正しい医療」と考える経営者としての信念を貫くことで生まれてきました。相澤院長は、「今の日本には地域密着型の病院がもっと必要」として、急性期の枠にこだわらず、やりたい医療ではなく、地域に求められる医療の必要性を訴えかけました。
「急性期らしさ」は係数に凝縮されている
GHCからはまず、相澤病院を支援するマネジャーの井口隼人が登壇。相澤院長の講演の流れを汲み、急性期病院における「急性期らしさ」を追求する上での短期的視点と中長期的な視点に分けて解説しました。
短期的視点については、DPCの機能評価係数II(以下、係数)に着目。係数は収益面においても、今後の戦略を立案するデータ分析においても、「『急性期らしさ』の考え方が凝縮された指標である」(井口)ためです。中でも今後、DPC病院(急性期病院)の経営を考える上で最重要となる係数である効率性指数と複雑性指数を取り上げ、その正確な理解と改善方法を示すための解説を行いました。その上で、この2つの指数をかけ合わることで自病院の「急性期らしさ」を把握し、(1)手術部門の強化(2)在院日数の短縮(3)退院支援の強化(4)集患―の4つの視点で「戦略的に対策を練られている病院が、真の急性期病院として生き残ることができる」(同)としました。
中長期的な視点としては、人材育成に言及。上記のような分析ができる人材が必要であることはもちろん、分析結果を院内に広めて改善活動を推進できる情報発信力のある人材も必要です。そのためには、経営層が経営分析スタッフの育成と、そのための投資が重要であると認識することが必要です。また、全スタッフがそれぞれ経営と医療の質向上を担う重要な立場にあるという、当事者意識とそれを推進していく仲間との連携が重要という意識も欠かせません。こうした院内風土を醸成し、人材育成を実践していくための研修事例として、旭川赤十字病院の事例を紹介しました。
病院経営者に求められる「3つの共有」
最後に登壇したGHC代表取締役社長の渡辺幸子は、リーダーとしての病院経営者に求められる資質を「3つの共有」に整理して解説しました。
最初の共有は、「医療を取り巻く環境の変化」です。病院大再編時代とも言える今、「なぜ、改革が必要なのか」という根本的な問いに、病院経営者が職員に答えられなければ話になりません。病床機能分化や急性期病床のダウンサイジングの必要性などを分かりやすく、繰り返し伝えることも重要ですが、急性期病院にとって今後最も重要な共有は、病病・病診連携にとどまらない「医療と介護の連携」です。渡辺は、「人は死ぬまでに医療から介護、介護から医療のサービス利用を繰り返す」という『ケアサイクル論』などを紹介しつつ、経営者自身はもちろん、「介護は別物」と考えがちな急性期病院の職員の思考を変革させる必要性を強調しました。
次の共有事項は、「病院が向かうビジョン(あるべき姿)」です。いつまでも急性期だけの枠で経営を考え、求められる医療ではなく、やりたい医療を提供していては、今後、生き残ることは難しいです。そのため、経営者はしっかり自病院の強みと弱みを見極め、ビジョンを示すことが求められています。場合によっては、再編や統合という病院にとっては厳しい現実が待ち受けているかもしれません。しかし渡辺は、経営的にも医療の質においても成功した病院の統合事例などを紹介し、まずは正確な現状分析とシミュレーションをし、自病院の立ち位置について決断を急ぐよう促しました。
最後に、「病院職員それぞれの使命と役割」です。渡辺は、「病院の未来のほとんどは経営者によって決まってしまう」と指摘した上で、具体的にはリーダーシップとビジョンの浸透度によって大きく4つの改善策があるとしました。例えば、明確なビジョンはあるものの、リーダーシップに欠ける病院であれば、重要な改善策は「誤解の払拭」です。リーダーシップに欠けるということは、抵抗勢力がいたり、無関心層がいるということです。そういう場合は、データを有効活用したり、コンサルティング会社など第三者の介入を試みたり、院長が率先して前面に立って問題のある診療科をヒアリングすることなどが有効でしょう。渡辺は、「いずれにせよ、病院の事情に合わせた改善策を実行することで、職員一人ひとりの使命と役割を共有し合い、組織としてのモチベーションを最大化することが、経営改善の王道」と締めくくりました。