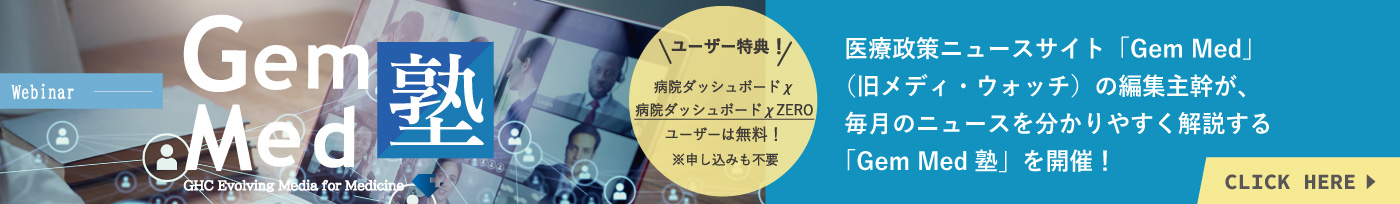加古川の病院統合、人員体制V字回復、5年半の「助走期間」がカギ
2015.1.30.(金)
全国的にも珍しい自治体病院と企業立病院の統合が兵庫県加古川市内で進んでいる。新たな経営母体となる地方独立行政法人が2011年4月に発足し、16年秋の新病院のオープンに伴って完全統合する。経営母体も得意分野も異なる病院同士の統合だが、最大の懸案だった医師不足を解消して人員体制を強化したことで、14年度には約2億円の増益を見込んでいる。完全統合までに5年半の「助走期間」を置いたのが功を奏したと、関係者たちは見ている。
【関連記事】
非営利ホールディングカンパニー型の新型医療法人
大事なのは、“大事なことを大事にすること”―スモルト氏
「一定の関与」か「強い関与」の二択制を提案―新型法人

「加古川中央市民病院」(仮称)は16年秋の開院を予定。JR加古川駅のそばに3万平方メートルの敷地を確保し、工事を進めている。16年6月に竣工予定。新病院は地上11階建て。28診療科体制でスタートし、「周産母子」「心臓血管」など5つのセンターを整備する。ベッド数600床は、兵庫県内で神戸・阪神間以外では最大規模。(地方独立行政法人加古川市民病院機構提供)
旧市民病院はもともと、地域でも有数の周産期医療の担い手だったが、2000年代後半に病院の存続自体が脅かされる事態に陥った。原因は医師不足。小児科・小児外科では常勤医20人余の体制を維持し、産婦人科医も常に10人前後を確保していたが、問題は内科だった。04年にスタートした新医師臨床研修の影響をもろに受け、もともと14人いた内科医が急激に減り始め、09年にはとうとう実質1人だけになった。
一方の旧神鋼加古川病院は、心筋梗塞など循環器系疾患の治療が得意分野だった。診療報酬の1日単価が7.2万-7.5万円と高水準で推移するなど、小規模ながら高密度な急性期医療を提供してきた。
これら2病院による統合は市側のアプローチがきっかけ。両方の病院に医師を派遣していた神戸大からの要請もあり統合を打診すると、神戸製鋼所も「地域医療の充実には協力したい」と応じた。
新たな経営母体として「地方独立行政法人加古川市民病院機構」が発足したのに伴い11年4月、旧市民病院は「加古川西市民病院」、旧神鋼加古川病院は「加古川東市民病院」として、それぞれ再スタートした。2病院は、16年秋に予定している「加古川中央市民病院」(仮称)の開院に伴い、完全統合するという流れだ。

機構の理事長には旧神鋼加古川病院の院長だった宇高功氏が就任した。宇高理事長がこれまで最も重視してきたのが、地方独立行政法人の本来の在り方で統合を進めるスタンスだ。このため理事長の責任と権限を明確化し、組織改革を進めた。一方で、2病院に勤務していたほとんどの市職員を市役所へ復職させた。これは、機構による病院運営の独立性を担保するのと、職員の専門性をアップさせるのが狙い。市職員は現在、市とのパイプ役の役割を中心に総務、経理、労務の関連部門に1人ずつ計3人が勤務するのみだ。
機構の発足から統合病院オープンまで、当初は6年を見込んでいたが、5年半に短縮させた。この助走期間を確保したことが、成否を分けた大きなポイントの一つだと機構では受け止めている。機構の発足から完全統合までに5年半の期間があったことで、職員の融和を進めたり、医薬品や医療材料の採用品目を統一したりと、完全統合までに「地ならし」を進めることができた。
機構事務部の櫃石秀信次長は、「初年度にいきなり新病院を立ち上げていたら、おそらく成功していなかった」と振り返る。

13年4月に2病院の責任者として統括院長を就任させたのも地ならしの一環だ。完全統合までの5年半、組織運営を円滑にするためで、14、15年度には看護部門や放射線部門、事務部門など各部署にも順次、統括責任者を配置した。自分たちのポストが脅かされかねないだけに、2病院の幹部たちにとって組織再編はセンシティブな試みだったはずだ。ただ、幹部らの世代交代と統合のタイミングが重なった。さらに、市職員の復職を促したことで事務部門の主要ポストを確保できていたため、一連の再編に反発や混乱はなかったという。
12年7月、共通の電子カルテシステムを導入したのも重要な布石だ。これによって2病院では、互いに診療支援し合いやすい体制が整った。それぞれが培ってきたノウハウを共有しようと人事交流に積極的に取り組んだり、医師向けに11年に取り入れたのを皮切りに、目標管理制度の導入を進めたりもしている。
組織統合に伴う一連の取り組みの効果が表れている。西市民病院の内科では14年4月現在、常勤医21人体制を確立できた。神戸大の要請に配慮しながら統合を進めたことで派遣を受けやすくなり、これが人員面でのV字回復を後押ししている。
看護師数も11年4月以降、右肩上がりだ。14年4月には西市民病院だけで345人と、10年前の旧市民病院の体制を100人近く上回る水準だ。人員体制の強化に伴って、西市民病院では13年から14年に掛けて、休眠病棟や人間ドックを次々と再開させた。さらに14年度には、NICU(新生児集中治療室)を退室した新生児の受け皿として27床のGCU(新生児回復室)を新たに整備した。
組織統合がもたらした効果はこれだけではない。ポジションの異なる2病院が1つになったことで、それぞれの得意分野で地域のシェアを拡大できた。中でも、旧市民病院がカバーしていた「小児」と「母子・周産期」のシェアは、12年度にはそれぞれ82%、93%とほぼ独占状態だ。旧神鋼加古川病院の得意分野だった「循環器」のシェアも65%を確保している。

同じ医療圏内には脳神経外科の専門病院や、3次救急に対応可能な県立の医療センターもあり、開業医を含めて医療関係者のつながりがもともと強い土地柄という。超高齢社会の到来をにらんで地域で医療再編が本格化するのに先立って、これらの医療機関による役割分担の方向性が固まりつつあると宇高理事長は感じている。
ただ、課題もある。現在は、「運営費負担金」として年に10億円を超える繰り入れを市から受けているが、国や市の財政再建が今後、本格化するのを念頭に置けば、公的資金に頼らない自立体質をつくり上げる必要がある。一連の改革を経て税財源から脱依存した国立病院機構の前例を参考に、市民病院機構でも官民の長所を取り入れながら改革を進める。
宇高理事長は「独立行政法人の柔軟性を最大限に生かし、自治体病院としての使命を果たしながら、持続可能な経営の自立体質をつくっていきたい」と話している。
13年秋に東市民病院が地域医療支援病院に認定され、西市民病院では同年、チーム医療の体制も充実できた。これらが追い風になったこともあり、2病院の連結による収支は順調だ。14年度には、新病院建設に伴う消費税負担を差し引いても約2億円の増益を見込んでいる。
新病院の建設工事は現在、急ピッチで進められている。病院統合の試金石として全国の関係者が成り行きに注目しているが、宇高理事長は「統合を決断するまでの背景や経緯はそれぞれ違う。アドバイスは難しい」。長い歴史を積み上げてきた病院同士の統合は一筋縄ではいかないということだ。