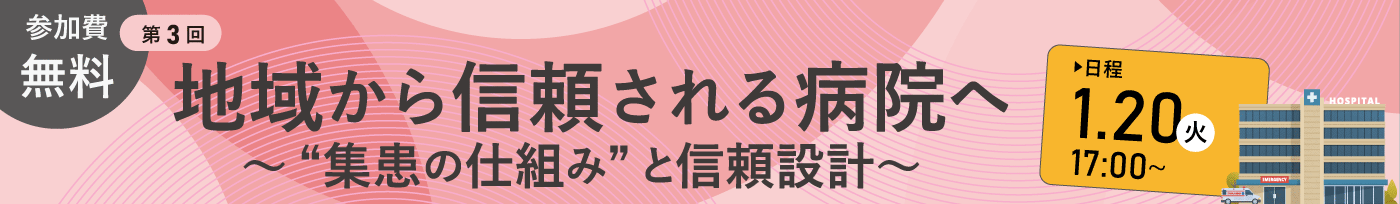「延命措置の中止」提案に6つのケースを想定-日病倫理委が見解
2015.5.28.(木)
寝たきりの高齢者の認知症が進んで周囲と意思の疎通が取れないなどの状態に陥り根治できないと医療チームが判断した場合、延命措置の中止を家族に提案する内容の「考察」を、医師や弁護士らによる日本病院会の倫理委員会がまとめました。延命措置の中止を提案するケースとして全部で6通りを想定していて、日病では、全国に約2420(4月現在)ある傘下病院にこうした内容を伝えます。
延命治療を中止する際の医師の免責事項を盛り込んだいわゆる「尊厳死法案」をきっかけに、終末期医療をめぐる議論が昨年、再燃したのを受けたものです。27日の記者会見で公表し、倫理委の松本純夫委員長(国立病院機構東京医療センター名誉院長)は「まだ指針の段階までいっていない」「現時点での見解」などと説明しました。
倫理委では、▽寝たきりの高齢者の認知症が進んで意志疎通が取れない▽高齢で経口摂取ができない▽胃ろうをつくり経口摂取への回復見込みがなく意思疎通もできない▽高齢で誤飲に伴う肺炎を起こし意識もなく回復が難しい▽末期がんで延命を望める有効な治療法がない▽脳血管障害で意識の回復が見込めない―の6つのケースを想定。
これらの状態に陥って現在の医療では根治できないと医療チームが判断したら、患者の延命措置を中止して苦痛を与えない「最善の選択」に切り替えるよう家族に提案してはどうかとの見方を示しています。ただ、アルツハイマー病など認知症患者の終末期は「見極めが困難」とも指摘しました。また、神経難病と重症心身障害のケースは「さらに難しい問題」と位置付けて議論を見合わせました。
倫理委のメンバーには、現場の医師や弁護士のほか日本尊厳死協会の幹部や大学教授らが加わっていて、見解では「社会保障の持続性が財政との関連で議論されるとき、必ず伸び続ける高齢者の医療費を支える世代間格差が問題になり、議論の終点が見えない」とも指摘しました。
延命治療に伴って家族の負担が膨らみ過ぎるケースもあるといい、松本委員長は会見で「実際に(医療機関との)トラブルがたくさん起きている」と話しました。
有志の国会議員が提唱しているいわゆる尊厳死法案は、延命治療を開始しなかったり、中止したりしても、患者が意思表示していることを前提に民事上、刑事上、行政上の責任を問われないようにする内容です。見解では、こうした内容は「国民から全面的な理解を得られない可能性がある」としていて、松本委員長は「法案化の前に十分な国民的議論が必要」との考えを示しました。
【関連記事】
14年度診療報酬改定に向け「病棟群単位の入院基本料」要望へ―日病協
疾患別リハの「専従常勤者」、非常勤の常勤換算容認を要望―四病協
14年の病院経営状況、赤字が77.8%に大幅増―日病、公私病連