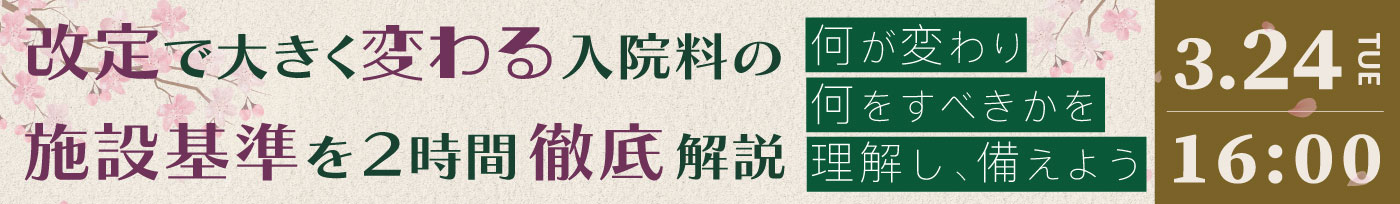肥満症治療薬の「ウゴービ」と「ゼップバウンド」、対象患者をしっかり鑑別するなど最適使用推進ガイドラインに沿った使用を—肥満学会
2025.5.13.(火)
肥満症治療薬の「ウゴービ」と「ゼップバウンド」が保険適用されているが、単なる肥満などの患者は対象にならない。「BMI35以上で併存疾患がある」などの対象患者をしっかり鑑別するなど最適使用推進ガイドラインに沿った使用が強く求められる—。
日本肥満学会が先頃、「肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメント」を改訂し、こうした考えを改めて強調しました(学会サイトはこちら)。
副作用を踏まえれば「糖尿病治療医と肥満症治療医の連携」などが強く求められる
2023年11月に肥満症(高血圧・脂質異常症・2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、「BMIが27以上で、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する」あるいは「BMIが35以上」に該当する場合に限る)を効能・効果とする「ウゴービ皮下注0.25mgSD、同皮下注0.5mgSD、同皮下注1.0mgSD、同皮下注1.7mgSD、同皮下注2.4mgSD」(一般名:セマグルチド(遺伝子組換え)」が保険適用されました。
また、本年(2025年)3月19日にも上記同様の肥満症を効能・効果とする「ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス(2.5mg0.5mL1キット)、同皮下注5mgアテオス(5mg0.5mL1キット)、同皮下注7.5mgアテオス(7.5mg0.5mL1キット)、同皮下注10mgアテオス(10mg0.5mL1キット)、同皮下注12.5mgアテオス(12.5mg0.5mL1キット)、同皮下注15mgアテオス(15mg0.5mL1キット)」(一般名:チルゼパチド)が保険適用されました。
両剤と同じ成分の2型糖尿病治療薬もありますが(セマグルチドを主成分とする「オゼンピック皮下注」、チルゼパチドを主成分とする「マンジャロ皮下注」)、両剤(ウゴービ、ゼップバウンド)は別の独立した臨床試験を行い「肥満症に対する効果と安全性」の検証プロセスを経て薬事承認→保険適用されています。
このため学会では、▼肥満症に対する十分な理解のもと、安全・適正に使用する▼健康障害を伴わない(したがって肥満症とは診断されない)肥満には用いない▼低体重や普通体重など適応外の体重者に対し美容・痩身・ダイエット等の目的で用いてはならない—点に十分留意する必要があると強調しています。
また、両剤(ウゴービ、ゼップバウンド)は「最適使用推進ガイドライン」の対象品目であり、ガイドラインを十分に理解して使用する必要があります。学会ではこうした点を含めて「両剤使用時の留意点」を下記のように整理しています。
【適応症】
(1)肥満症について
▽肥満は脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した結果「BMI25以上」を示す状態で、「肥満症」とは異なり、これのみでは両剤の適応とはならない
▽肥満症は「肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測され医学的に減量を必要とする疾患」と定義され(肥満症診療ガイドライン 2022)、具体的には、「肥満(BMI25以上)+減量によりその予防や病態改善が期待できる肥満症の診断基準に必須の11の健康障害のいずれかを伴うもの」である
(肥満症の診断基準に必須の11の健康障害)
・耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常など)
・脂質異常症
・高血圧
・高尿酸血症、痛風
・冠動脈疾患
・脳梗塞、一過性脳虚血発作
・非アルコール性脂肪性肝疾患
・月経異常、女性不妊
・閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満低換気症候群
・運動器疾患(変形性関節症:膝関節・股関節・手指関節、変形性脊椎症)
・肥満関満関連腎臓病
(2)両剤の適応となる肥満症
▽両剤は「肥満症」と診断され、かつ「高血圧、脂質異常症または2型糖尿病のいずれか」を有し、以下のいずれかに該当する場合に限り適応となる
・BMI27以上で、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する
・BMI35以上である場合である
→すなわち、「肥満症+BMI35以上+高血圧・脂質異常症・2型糖尿病のいずれか」、あるいは「肥満症+BMI27以上35未満+高血圧・脂質異常症・2型糖尿病のいずれか+11の健康障害(上記)のいずれか2つ以上」の場合に保険適用となる
(3)両剤使用時に確認すべき注意点
▽患者が肥満症と診断され、かつ(2)の適応基準を満たすことを確認した上で適応を考慮する
▽肥満症治療の基本である食事療法(肥満症治療食の強化を含む)・運動療法・行動療法をあらかじめ行っても十分な効果が得られず、薬物治療の対象として適切と判断された場合にのみ考慮する
▽内分泌性肥満、遺伝性肥満、視床下部性肥満、薬剤性肥満等の症候性(2次性)肥満の疑いがある患者においては原因精査と原疾患の治療を優先させる
【安全性】
(1)糖尿病治療との関連
▽両剤は糖尿病の有無にかかわらず、単独で使用する場合には「低血糖」を生じるリスクは少ない
▽ただし、「他の血糖降下薬、特にインスリン製剤、スルホニル尿素(SU)薬、グリニド薬と併用する場合には、低血糖を来す可能性が増大する」ことに十分な注意を払う必要がある
▽血糖降下薬を不適切に減量すると、「望ましくない高血糖や急性代謝障害を引き起こす」可能性もある
↓
▽糖尿病治療が行われている患者には、「投薬を含めた治療状況を十分に把握した上で両剤による治療を行う」ことが望ましく、糖尿病治療を行っている医師が処方するか、糖尿病治療を行っている医師と十分に連携をとった上で処方するべきである
(2)副作用について
▽添付文書上、「重大な副作用」には▼低血糖▼急性膵炎▼胆嚢炎▼胆管炎▼胆汁うっ滞性黄疸—が示されており、これらの副作用の発現にも注意すべきである
▽同じく「特定の背景を有する患者に関する注意」として「高齢者」が示されており、両剤による過剰な体重減少にも注意を払う必要がある
▽特に高度肥満症においてはメンタルヘルスの変化にも注意し、「自殺企図または自殺念慮を有する、あるいは既往のある患者」には格別の留意が必要である
▽「甲状腺髄様がんの既往のある患者や、甲状腺髄様がんまたは多発性内分泌腫瘍症2型の家族歴のある患者」に対する両剤の安全性は確立しておらず、米国では「禁忌」であることにも留意する必要がある
(3)投与の中止や中断
▽両剤の中止によって、▼顕著なHbA1cの上昇▼急激な肝機能の悪化▼リフィーディング症候群—を来す可能性がある
▽両剤の使用継続や中止は医師の管理下で行われる必要があり、中止後の健康障害の変化にも十分に注意を払う必要がある
▽健康障害の悪化時には両剤の再開を含めた適切な対応をとることが望まれる
【最適使用推進ガイドラインの遵守】
▽両剤は最適使用推進ガイドラインの対象品目であり、保険診療の中で使用する場合には、、最適使用推進ガイドラインに記載されている「施設・医師要件」「患者要件」「投与の継続・中止の判断基準」などを遵守する必要がある
●ウゴービの最適使用推進ガイドライン
●ゼップバウンドの最適使用推進ガイドライン
【関連記事】
肥満症治療薬の「ウゴービ皮下注」の使用可能医療機関の考え方、ストーマ合併症加算の詳細を明確化―疑義解釈20【2024年度診療報酬改定】
訪問看護ステーション、「年間請求額が高額・1件当たり請求額が高額」等のケースではサービス内容確認等のため指導等実施へ—中医協総会(1)