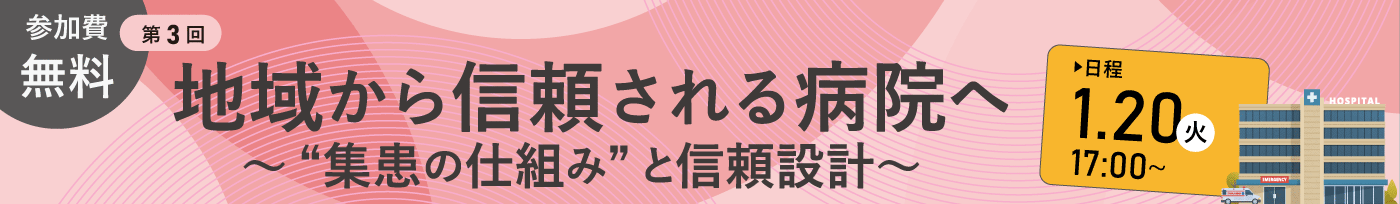健保組合加入者の特定健診(メタボ健診)・特定保健指導の実施状況は向上しているが、被扶養者(家族)ではまだ低調―2023年度健保連調査
2025.2.20.(木)
健康保険組合加入者における「特定健診」(メタボ健診)や「特定保健指導」の実施状況を見ると、徐々に向上してきている。しかし、「被扶養者」(家族)で低調な状況そのものは変わっていない—。
健康保険組合連合会が2月12日に、2023年度の「特定健診・特定保健指導の実施状況」に関する速報値を公表しました(健保連のサイトはこちら)(前年度の記事はこちら)。被扶養者の健康水準向上に向けて「特定健診や特定保健指導の実施率向上」に対する取り組みに期待が集まります。
2023年度の特定健診実施率は80.8%に上昇
特定健診は、40-74歳の人を対象としたメタボリックシンドロームに着目した健診です(いわゆるメタボ健診)。主に、▼服薬歴、喫煙歴の有無▼身長・体重・BMI(Body Mass Index)・腹囲▼血圧▼尿(尿糖・尿タンパク)▼血液(脂質・血糖・肝機能)―などを調べます。高齢化の進行、生活習慣の変化によって、糖尿病などの生活習慣病の有病者・予備群が増加していることを重くみて、2008年4月から導入されました。
2023年度の健保組合における特定健康診査対象者は約979万人で、このうち受診者数は約791万人、実施率は80.8%となりました。前年度に比べて0.5ポイント向上しています。
また被保険者(いわば大企業サラリーマン本人)の受診率は90.4%(前年度比0.1ポイント低下)、被扶養者(家族)では48.1%(同0.6ポイント向上)となりました。向上してはいるものの「被扶養者の健診受診率が低い」状況そのものは変わっていません。
さらに組合別にみると、単一組合(大企業が独自に設立する健保組合)の受診率は81.5%(前年度から0.5ポイント上昇)(このうち被保険者91.0%(同0.2ポイント低下)、被扶養者51.7%(同1.1ポイント上昇))ですが、総合組合(同一業種等の複数企業が設置する健保組合)では79.5%(同0.7ポイント上昇)(このうち被保険者89.5%(同0.2ポイント上昇)、被扶養者41.1%(同0.1ポイント上昇))とやや低くなっています。
2023年度の特定保健指導実施率は33.9%に上昇
特定健診によって「生活習慣の改善が必要である」と判断された場合には、特定保健指導が行われます。具体的には腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上で、▼空腹時血糖値110mg/dL以降▼中性脂肪150mg/dL以上、HDLコレステロール40mg/dL未満のいずれか、または両方▼最高血圧130mmHg、最低血圧85mmHg以上のいずれか、または両方―のうちいずれか1つまたは2つに該当する人などが「動機付け支援」、3つに該当する人などが「積極的支援」を受けることになります。
特定保健指導対象者数は約142万人で、特定保健指導終了数は約48万人。実施率は33.9%となり、前年度に比べて0.7ポイント上昇しています。
保健指導レベル別の実施率は、積極的支援28.4%(前年度比0.5ポイント向上)、動機づけ支援37.3%(同3.0ポイント向上)となりました。被保険者・被扶養者別に見ると、次のような状況で、やはり被扶養者で低調です。
【被保険者】
▽積極的支援:31.1%(前年度から0.7ポイント上昇)
▽動機づけ支援:39.7%(同0.6ポイント上昇)
【被扶養者】
▽積極的支援:14.7%(同0.6ポイント上昇)
▽動機づけ支援:20.2%(同0.2ポイント上昇)
【関連記事】
健保組合加入者の特定健診(メタボ健診)、特定保健指導の実施状況は向上してきたが、被扶養者でまだ低調―2022年度健保連調査
健保組合加入者の20.1%は血圧に、33.5%は脂質に、6.0%は血糖に、13.1%は肝機能に問題があり、医療機関受診が必要―健保連