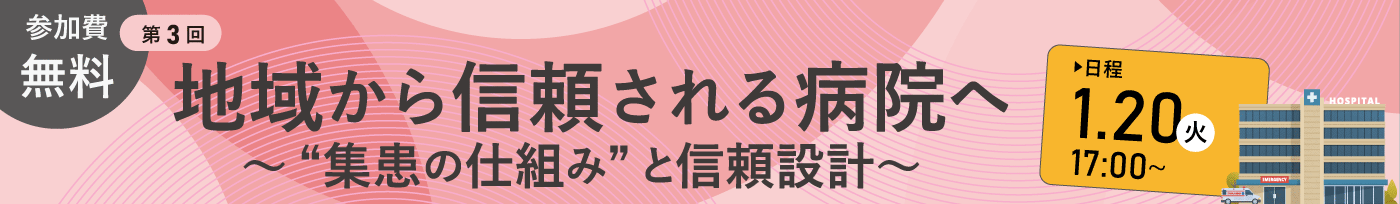宿直医師の「複数病院での兼務」、医師の負担増・家族とのトラブル・救急受け入れ制限等の問題解決しなければ認められない—日慢協・橋本会長
2025.6.26.(木)
規制改革推進会議で「宿直医師の複数病院での兼務」等が検討課題に挙がっているが、▼医師の負担が増加する▼患者・家族とのトラブルが生じる▼救急受け入れを制限しなければならない—などの問題を解決しなければ、認めることはできない—。
日本慢性期医療協会の橋本康子会長が6月24日に、こうした考えを明らかにしました。
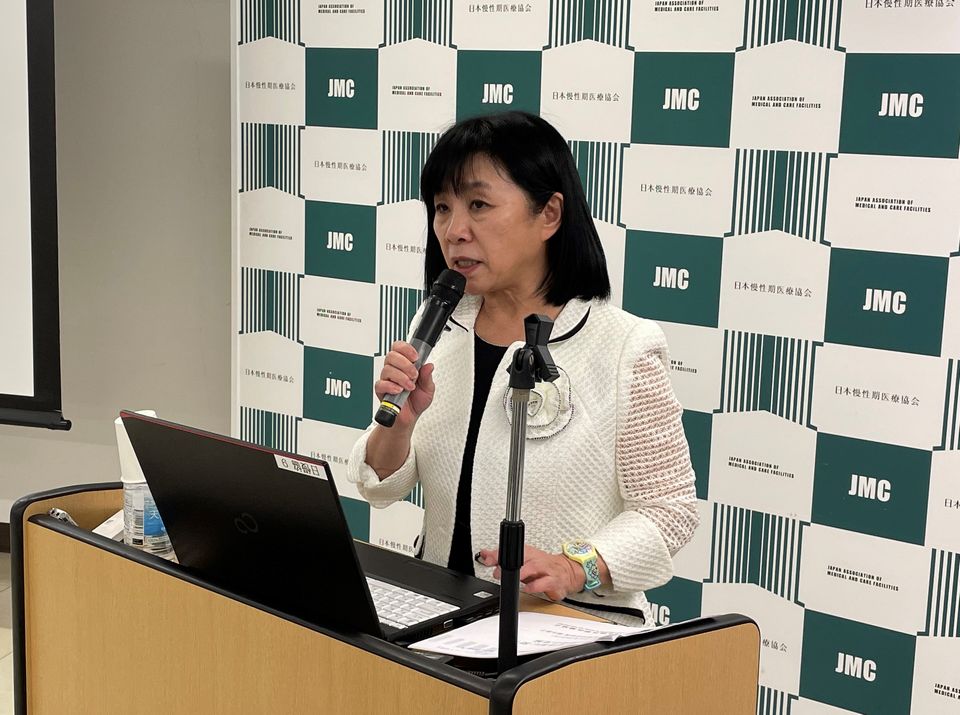
6月24日に「医師の宿直」についての見解を明らかにした日本慢性期医療協会の橋本康子会長
慢性期病院での宿直、「夜間の診療需要、医師の対応が限定的」と言えるのだろうか
石破茂内閣が6月13日に規制改革実施計画を閣議決定しました。
その中で、地域の慢性期医療を担う一部の病院などから▼夜間の診療需要が限定的で、宿直医師が常に対応を求められる状況ではない▼看護師による患者状態の適切な把握の下、ICT技術の活用により遠隔でも医師は適切な指示(救急搬送指示を含む)を行える場合がある—ため、患者の安全性を確保することを前提として、一定要件下で「1名の医師が複数の病院の宿直対応を兼務で行うことを可能とする」ことを求める要望があり、この点について遅くとも「2027年度中に結論を出して、措置する」ことが規制改革推進会議から厚生労働省へ指示されました。
日慢協では、「夜間の診療需要が限定的で、宿直医師が常に対応を求められる状況ではない」との病院指摘(ちなみに「日慢協会員病院ではない」と橋本会長は指摘)が妥当なものかを検証するために、日慢協会員病院を対象に緊急調査を実施。
具体的には156施設(3万1032床・平均198.9床)を対象に、本年(2025年)5月26日から6月8日の2週間における▼宿直医師数▼宿直時間▼電話対応件数▼現場対応(診察・処置、転院対応、救命措置、看取り、ほか)件数—を調査。次のような状況が明らかになりました。
▽1病院・1日当たりの電話対応:0.6件(全体・2週間で1297件あったものを、1病院・1日当たりに換算)
▽1病院・1日当たりの現場対応:1.1件(全体・2週間で2405件あったものを、1病院・1日当たりに換算)
(内訳、端数処理の関係で合計と合致しない)
・診察・処置:0.8件
・転院対応:ゼロ件
・救命措置:ゼロ件
・看取り:0.2件
・ほか:ゼロ件
このデータからは「毎日、夜間に緊急対応が行われて」おり、「夜間の診療需要が限定的で、宿直医師が常に対応を求められる状況ではない」とは言えないように思えます。
ただし、調査対象には一般病床(急性期病床)も含まれています。これでは「救急患者を受け入れることもあり、病態の不安定な急性期患者を診る病院のデータが含まれているため、宿直の負担が大きいのではないか」との反論も出てきそうです。
そこで橋本会長は、上記回答病院の中から、▼療養病棟▼回復期リハビリ病棟▼地域包括ケア病棟—のいずれかのみで運営している病院(60病院・7984床)を抽出して、同様の分析を実施。「急性期病院を含まない。回復期・包括期・慢性期の病院に絞った」データと言えますが、そこからは次のような状況が明らかになりました。
▽1病院・1日当たりの電話対応:0.5件(全体・2週間で397件あったものを、1病院・1日当たりに換算)
▽1病院・1日当たりの現場対応:0.7件(全体・2週間で553件あったものを、1病院・1日当たりに換算)
(内訳、端数処理の関係で合計と合致しない)
・診察・処置:0.5件
・転院対応:ゼロ件
・救命措置:ゼロ件
・看取り:0.1件
・ほか:ゼロ件
急性期病院を含めたデータに比べると現場対応件数は若干少なくなりますが、それでも「3日に2回以上、毎日に近い度合いで、宿直医師が現場対応を行っている」状況が分かります。
2週間という限定的な調査ではありますが、やはり「夜間の診療需要が限定的で、宿直医師が常に対応を求められる状況ではない」とは言えないようです。
現場からは「宿直医師確保が困難であり、合理的・現実的な宿直体制を検討してほしい」との意見が出る一方で、「宿直医師配置は病院である限り必須である」「患者とトラブルが生じた場合には、病院の管理者(院長等)に責任が及ぶ」との声も出ています。
また、後者の「回復期・包括期・慢性期の病院に絞ると、1病院・1日当たり0.7件の現場対応が行われている」とのデータに基づけば、上記要望の「複数病院での宿直兼務」では▼2病院を1人で兼務した場合には1日当たり1.4件の現場対応が必要となる▼3病院を1人で兼務した場合には1日当たり2.1件の現場対応が必要となる—との計算になります。
現場対応として「診察・処置」の度合いが多くなっていますが、橋本会長は「数時間かかることもある」と指摘(処置をして終わりではなく、容態が落ち着いたのかなどを確認する必要がある)。また複数病院間に距離があれば「移動時間」もかかります。
さらに「片方の病院で現場対応している」間に、「もう片方の病院で処置等が必要な患者が発生する」可能性もあり、病院の規模が大きく、兼務病院の数が増えるほど、この可能性は高くなります。
複数病院での宿直勤務、医師の負担・働き手の確保、訴訟リスク等の問題が山積
こうした実態調査結果なども踏まえて橋本会長は、「1人の医師が、複数病院の宿直を兼務する」に当たっては、次のような課題が想定されると見通しました。
(1)時間の課題
▽現場対応が必要な患者が同時に発生した場合にどう対応するのか
▽病床規模が大きく、病院間の距離が開くほど、時間の課題が大きくなる
(2)業務の課題
▽病院によって「処置に必要な機器」等の準備場所が異なり、探すだけで時間がかかる。さらに普段使っていない機器などである場合には、操作上の問題も生じる
▽病院ごとに電子カルテが異なるケースが多く、対応しなければならない患者の診療記録把握が容易には行えない
▽「患者の状態などを十分に把握している夜勤看護師」が常に配置されているとは限らない(結果、患者の状態を十分に把握できず、適切な処置などを行えない可能性もある)
(3)働き手確保の課題
▽上記計算のように「毎日1.4件の現場対応が必要な宿直」(病院間の移動などもあり、大きな責任も伴う)業務を希望する医師がいるのだろうか、という問題もある
(4)患者家族対応の課題
▽「片方の病院で対応していた」「移動に時間がかかった」などで、緊急対応が行えなかった場合には、患者・家族との間でトラブルが生じ、訴訟にまで発展しかねない
(5)救急患者受け入れの課題
▽兼務では「夜間の対応力が限定される」こととなり、日慢協の目指す「慢性期救急」(高齢者救急)対応を制限しなければならなくなってしまう
▽その場合、地域の急性期病院の救急患者受け入れ負担が過重になってしまう
いずれの課題も非常に重いものです。(1)(2)の課題は、患者にとっては「状態が悪化した場合に、適切に対応してもらえないのではないか」との不安につながります。
また(2)(3)に関しては、「そういった困難な業務に携わりたい」という医師がどこまでいるのだろうかという疑問につながります。橋本会長は「すでに若手でも『宿直はしたくない』と考える医師が増えており、さらに兼務で負担が増す宿直を希望する医師がいるのだろうか」とコメントしています。
さらに、医療者、とりわけ病院経営者にとっては(4)の課題が重視されるところですが、患者の立場になっても、やはり「病院に入院していたのに、状態悪化に対応してもらえなかった」という不満は非常に大きなものとなるでしょう。
また(5)では「地域医療に既にある救急対応の課題」を、より大きくしてしまう可能性もあります。
橋本会長は「宿直医師の確保が非常に難しく、規制を緩和してほしい」との声は十分に理解できるとしたうえで、「本件については2027年度中に結論を出すとしているが、こうした課題をしっかり検討し、解決してからでなければ、『1人の医師による複数病院の宿直兼務』は難しい」との考えを示しています。
課題を解決しないままに進めれば、「宿直医師の確保が難しい」→「宿直のルール緩和(複数病院での兼務可など)をする」→「個々の宿直医師の負担が重くなる」→「宿直医師の確保がより難しくなる」という負のスパイラルに陥る可能性が高く、また「医療の質低下」「訴訟リスクの増大」「地域医療、とりわけ夜間救急医療の崩壊」などにつながってしまう可能性もあります。
今後、社会保障審議会・医療部会などで議論されると思われますが、どういった議論が行われるのか注目する必要があります。
【関連記事】
介護福祉士が「介護現場で働く」場合と、「医療機関で看護補助者として働く」場合とで、同一処遇となるような仕組みが必要—日慢協・橋本会長
「ケアプランの医療的部分を病院の他職種チームが作成」することでケアマネの負担軽減と、ケアプランの質向上を実現せよ—日慢協・橋本会長
スタッフが育児休業等を取得した際にも人員基準をクリアできるよう、「代替人員」雇用の助成金対象医療法人拡大を—日慢協・橋本会長
「リハビリの視点・知識・技術」を持った介護職員(リハビリ介護士)の養成・配置により寝たきり高齢者の増加を防止せよ—日慢協・橋本会長
入院からのより円滑な在宅復帰を目指し、【院外リハビリ】の算定可能時間延長・実施目的拡大を図るべき—日慢協・橋本会長
介護医療院入所者の「実態」踏まえた介護報酬を、介護医療院は「医療が必要な重度要介護者」の最後の砦—日慢協・橋本会長他