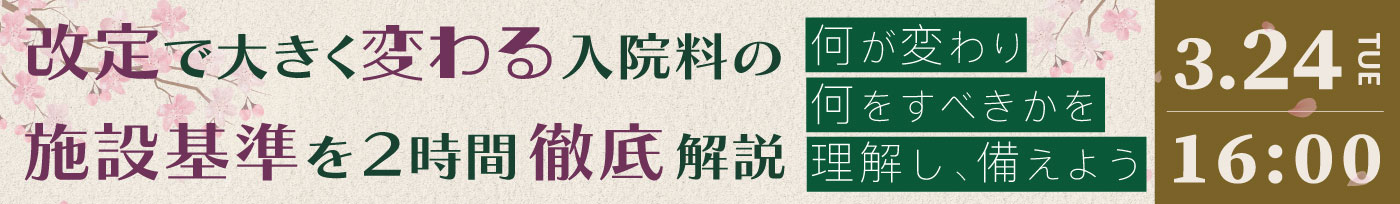2026年度診療報酬改定に向けて、「新規医療技術の保険適用」「データに基づく既存技術の再評価」の検討もスタート―中医協(2)
2025.2.20.(木)
安全性・有効性が確認された医療技術については、原則として保険適用が行われる。2026年度の次期診療報酬改定でも学会等からの提案を踏まえて、新規医療技術の評価を行い保険適用すべきか否かを決する—。
また既存の医療技術のうち「優れた医療技術として診療ガイドラインに位置付けられているもの」「有効性・安全性の評価に向けたレジストリ登録が義務付けられているもの」などについては、その効果を検証し、必要に応じた再評価(点数引き上げなど)を検討していく—。
2月19日に開催された中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員会、および引き続き開かれた総会では、こうした方針も了承されました。関係学会等から示される「新規医療技術の保険適用に係る提案書」「既存医療技術の再評価に向けた報告書」を踏まえて、専門家会合(中医協の下部組織である医療技術評価分科会)で審議が進められます(提案書は6月上旬締め切り、報告書は7月上旬締め切り)(同日の「造血器腫瘍および類縁疾患ゲノムプロファイリング検査」に関する記事はこちら)。
目次
2026年度診療報酬改定における医療技術評価の考え方を確認
医療・医学の水準は日進月歩しており、その成果・果実を広く国民が享受できるよう、前述のように安全性・有効性を確認したうえでの保険適用が順次進められます(この点、医療保険制度の持続可能性を考慮し、保険適用の在り方を考えるべきとの議論もある点に留意が必要である)。
2年に一度行われる診療報酬改定では、多くの新規医療技術の保険適用が行われますが、効率的かつ公平・公正な検討を行うために2018年度の診療報酬改定から、▼関係学会から提案された新規医療技術▼先進医療で実施されエビデンスの整った新規医療技術―について、中医協の下部組織である診療報酬調査専門組織「医療技術評価分科会」で評価を実施。その結果を中医協で審議し、どの技術を保険適用するべきかなどを決するという仕組みが設けられています。専門家で構成される医療技術評価分科会において、より幅広い視点・公平な視点で保険適用の可否を検討するものです。
また、より科学的な視点に立って検討を行うために、2022年度診療報酬改定からは次のような仕組みも導入されました。
(1)診療ガイドライン等に基づく医療技術の評価
(2)レジストリに登録され、実施された医療技術の評価
まず(1)は、学会からの「この技術を保険適用してほしい」との提案書の中に「診療ガイドライン等における当該医療技術の位置づけなどを明示する」ことを求めるものです。診療ガイドラインに位置づけられている技術は「専門家の間で有用性・安全性が相当程度確認されている」と言え、優先的に保険適用していくことが国民にとって有益と考えられます。2024年度の前回改定ではガイドライン等で記載のあった技術は113件でした。
また(2)は、「新たな医療技術が、既存の技術に比べてどれだけ優れているのか」を確認するために、学会に症例登録(レジストリ登録)を求めるものです。このデータを活用し「既存技術よりも優れた効果がある」と確認できれば、診療報酬点数の引き上げなどを検討することになります。2024年度の前回改定では、35件の医療技術についてレジストリを用いた効果検証が行われています。
2月19日の中医協では、2026年度の次期診療報酬改定に向けて「2024年度診療報酬改定と概ね同様の考え方」(一部修正)に立って、新規医療技術に関する保険適用の可否を検討する方向が確認されました。その大枠は次のとおりです。
▽評価対象となるのは▼診療報酬点数表の「医学管理等」(Bコード)から「病理診断」(Nコード)に該当し、「アウトカムが改善する」などの有効性をデータで示すことができる医療技術▼先進医療で実施されている医療技術▼保険医療材料等専門組織で審議された医療技術のうち「医療技術評価分科会での審議が必要」とされた医療技術—に限定する
▽学会等は、「保険適用の必要がある」と考える医療技術について、▼技術名とその内容▼主たる診療科▼対象疾患▼類似の医療技術▼概要▼実績▼保険適用が必要な理由▼診療ガイドラインでの位置づけ▼予想される影響額―などを提案書に記載し、厚労省に提出する
▽提案書には「当該医療技術の保険適用・増点に関連して削除や減点が可能と考えられる既存の医療技術」「現に当該医療技術の対象となる患者に対して行われている医療技術」も記載する
間もなく受け付けが始まり、厚生労働省保険局医療課医療技術評価推進室の木下栄作室長は「6月上旬まで学会からの提案書を受け付ける」考えを示しています(具体的な日付はさらに調整)。「この技術を保険適用してほしい。この技術について有用性が認められたため、増点をしてほしい」と考える学会等は急ぎ提案書を準備する必要があります。
新規の医療技術が登場した場合、「既存技術は効果が劣り、使われなくなる(新規技術に置き換わる)」という事態も生じえます。新規技術の提案では、この点についても記載することが求められ、データを踏まえて「既存技術の減点や、保険からの削除」なども併せて検討されます。この点について支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、後述する再評価とも絡めて「新規技術の保険適用・増点は、既存技術の削除・減点とセットで行う必要がある。医療保険制度の維持という視点を持って、新規技術の評価を行ってほしい」と要望しています。
既存医療技術(146件)についてデータをもとに効果などを再検証
また医療技術評価分科会では、「すでに保険適用されている医療技術の評価」(再評価)も行います。技術の効果を検証し「優れていれば増点を、効果が芳しくなければ減点を検討していく」ことになります。
▽2024年度診療報酬改定で▼「ガイドライン等で記載あり」とされた技術(116件)▼レジストリの登録を要件として保険適用された技術(40件)—について、関係学会からの提案とは別に「医療技術評価分科会での再評価」の対象とする
▽学会からの提案書様式について、臨床的位置づけや根拠の変化の有無を記載することとする
▽医療技術の再評価方法について検証を行うとともに、「既収載技術の再評価方法のあり方」について研究・検討を進める
こちらも間もなく受け付けが開始され、木下医療技術評価推進室長は「医療技術の再評価にかかる報告書については7月上旬まで受け付ける」考えを示しています(具体的な日付はさらに調整)。この点、上記の技術については報告書の提出が「義務」となっている点に留意が必要です。支払側の松本委員は「学会提案またずにエビデンスの評価を積極的に進め、再評価を着実に行ってほしい」と要望しています。
このほか、「医療技術の体系的評価」を進める(STEM7)ために、1つのKコード(手術に関する診療報酬点数のコード)に対して「手術部位ごとにSTEM7が分類されている整形外科領域」の一部術式について体系化が可能と考えられたことを踏まえ、2024年度診療報酬改定で整形外科領域の同様の術式について検証が行われており、2026年度診療報酬改定に向けても必要な検証を進める方針も確認されました(関連記事はこちらとこちら)。
2025年度薬価改定内容を正式決定、最低薬価引き上げ等踏まえ適切価格での流通を
なお、2019日の中医協総会では「2025年度薬価基準見直し」内容を正式決定しています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。
2025年度薬価見直しの中では「最低薬価の引き上げ」が行われてますが、厚労省医政局医薬産業振興・医療情報企画課の水谷忠由課長(医薬産業振興・医療情報企画課セルフケア・セルフメディケーション推進室長併任)は「最低薬価が引き上げられたにもかかわらず、値引き販売・購入するようなことがあっては本末転倒である。適正な取引を行うよう関係者に周知していく」考えを強調しています。
【関連記事】
2025年度薬価中間年改定の内容を実質決定、インフル流行踏まえ解熱鎮痛薬等も急遽不採算品再算定の対象に—中医協総会(2)
2025年度薬価中間年改定の骨子を決定、能登半島地震被災病院等でDPC機能評価係数IIの配慮措置—中医協総会(2)
2025年度薬価中間年改定論議が実質決着、9320品目の薬価を引き下げ、新薬創出等加算の「累積控除」を初実施—中医協・薬価専門部会
2025年度の薬価中間年改定(薬価引き下げ)を実施すべきか?実施する場合の対象品目・ルールをどう考えるか?—中医協
医薬品のイノベーション評価・安定供給に逆行しないよう、2025年度に薬価の中間年改定(=薬価引き下げ)は中止をと医薬品業界—中医協
規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審
2024年度の薬価乖離率は5.2%、過去改定に倣えば「乖離率が3.25%以上の医薬品」は2025年度薬価引き下げの対象に—中医協・薬価専門部会
2025年度薬価中間年改定、「医薬品の安定供給、薬価下支え」と「国民皆保険維持」とのバランスをどう考えるか—中医協・薬価専門部会
2025年度薬価中間年改定、「新薬開発に向けたイノベーション評価」と「国民皆保険維持」とのバランスをどう考えるか—中医協・薬価専門部会
2025年度の薬価中間年改定、「2024年度薬価制度改革のイノベーション評価方向に逆行する」と医薬品業界は反対姿勢—中医協・薬価専門部会
「2025年度の中間年薬価改定」、行うべきか否かも含めた議論開始、連続改定による負の影響を懸念する声も—中医協・総会(2)
2024年度薬価・材料価格・費用対効果評価の制度改革内容を決定、23成分・38品目の医薬品を市場拡大再算定—中医協総会(2)
2024年度の薬価制度・材料価格制度・費用対効果評価制度の「改革骨子」固まる、年明けに詳細な改革案決定へ—中医協