2026年度診療報酬改定に向け入院料引き上げ、救急搬送を多く受け入れる地域包括ケア病棟の評価充実等検討を―地ケア推進病棟協・仲井会長
2025.8.20.(水)
2026年度の次期診療報酬改定に向けて、「入院料の引き上げ」や「各種専従要件の緩和」、「救急搬送患者等を多く受け入れる地域包括ケア病棟の評価充実」、「地域包括医療病棟の救済措置延長や新たな評価軸の設定」、「急性期病棟と地域包括ケア病棟のケアミクス併存・継続」などを検討すべき—。
また2028年度の次々期診療報酬改定を見据え、「多数疾患を抱えるマルチモビティティ患者の重症度評価」に向けた調査・研究を今から進めるべき—。
地域包括ケア推進病棟協会(以下、協会)の仲井培雄会長が8月19日にオンライン記者会見を開催し、8月12日に厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長に宛ててこうした要望を行ったことを明らかにしました(協会サイトはこちら)。
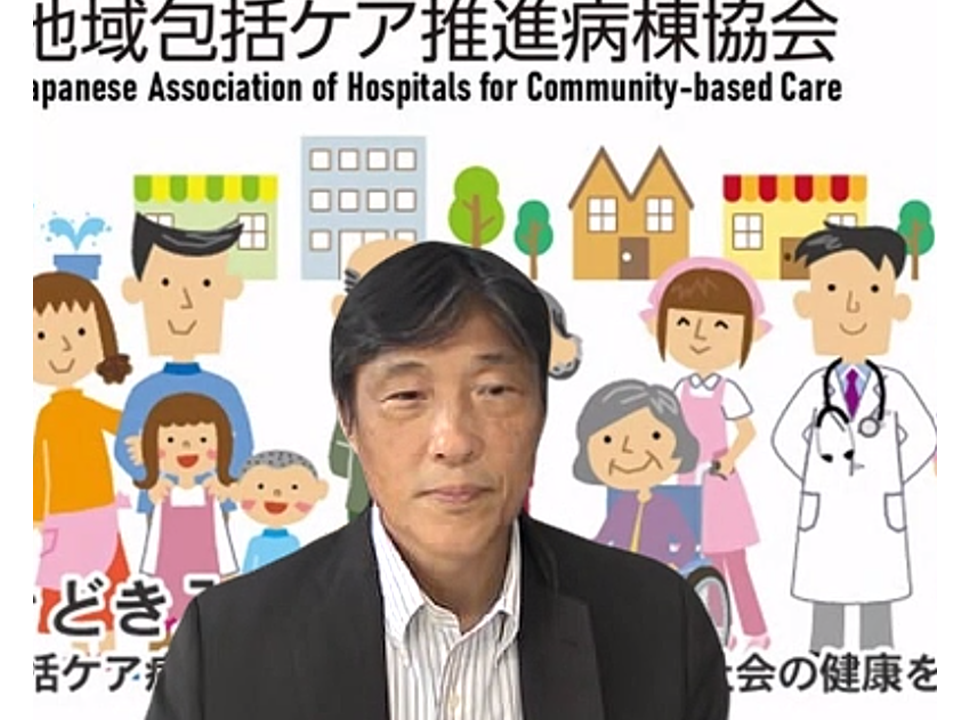
8月19日に記者会見に臨んだ地域包括ケア推進病棟協会の仲井培雄会長
2028年度の次々期診療報酬改定見据え、今から「マルチモビディティ患者の評価」研究を
2026年度の診療報酬改定に向けた議論が、中央社会保険医療協議会を中心に進められています。
そうした中で地域包括ケア推進病棟協会の仲井会長は、林医療課長に宛てて次のような要望を行いました。2026年度改定だけでなく、その次の「2028年度診療報酬改定」も見据えた内容となっています。
まず地域包括ケア病棟・地域包括医療病棟に共通する内容として、次の4点を要望しています。
(1) 入院料を大幅に引き上げる(物価、人件費、委託費、建築費等が急騰する中で病院経営の持続性が脅かされており、質の高い医療・ケアの継続、安定した医療提供体制を確保する必要がある)
(2) チーム医療に関する「専従要件」をなくし、兼務を認める(人材確保が厳しさを増す中で、▼必要な資格▼一定の経験年数—を要件とし「専任での複数業務の兼務」を認めることで、職員のスキルを最大限に活用でき、チーム医療全体の強化につながる)
(3) 救急患者を3次救急まで「迎え」に行き、転院を受け入れた場合の評価を創設する(【救急患者連携搬送料】の利用は低調であり、また地域包括ケア病棟での【在宅患者支援病床初期加算】を活用した患者受け入れも進んでおらず、転院患者を「迎え」に行く場合の評価を検討すべき)
(4) 2028年度改定を見据えて、「マルチモビディティ患者を受け入れた場合の評価」を検討すべき
このうち(4)のマルチモビディリティとは「多くの疾患を抱えている状態」です。例えば、▼CPOD(慢性閉塞性肺疾患)▼高血圧▼糖尿病▼脳梗塞の後遺症—が併存する患者では、「抗血栓薬、血圧降下薬をはじめとする多種類の薬剤の服用管理」、「インスリン製剤の管理」、「シーパップ(CPAP)による呼吸管理」、「ADL低下に伴う転倒・転落の防止」など複合的な治療・管理が必要となります。それぞれの疾患に対する治療・管理そのものは、それほど難しくありませんが、これらが複合した場合には、その治療・管理が「極めて複雑で難しい」ものとなることは述べるまでもないでしょう。
仲井会長は「マルチモビディティ患者の治療・管理は、当然、『単に肺炎で入院した若年患者』のそれとは手間のかかり方が大きく異なってくるが、現在の重症度、医療・看護必要度では十分な評価がなされていない。そうした点について、2028年度の次々期診療報酬改定での十分な評価を睨んで、今から調査・研究を行うべき。新たな地域医療構想でも、この点が重要になってくる」とコメントしています。
また、地域包括ケア病棟については、2014年度診療報酬改定での創設から10年超が経過する中で、様々な課題も浮かび上がってきている点を踏まえて、次のような要望を行っています。
▽【看護職員配置加算】(看護職員を加配した場合の加算)に関し、「看護職員と他職種との業務分担」および「柔軟な勤務体制の工夫」に着目した要件緩和を行ってほしい
→看護師の早出・遅出業務を他職種が専門性を活かして代替した場合に、その職員を加算の対象とみなす。その際「ICT等の技術活用による業務負担軽減」「医療安全管理」「感染対策」の実施を要件とする
▽救急搬送患者を地域包括ケア病棟で直接受け入れた場合、SOFAスコア等の指標を活用した「数日間のトリアージ期間」を設け、その期間中に病態が悪化した場合、1回に限り「地域包括ケア病棟(A)→急性期病棟(B)→地域包括ケア病棟(C)」における、「Cでの地域包括ケア病棟入院料算定」を認める床を経た後の地域包括ケア病棟への再入棟を認め、地域包括ケア病棟入院料を算定可能としてほしい
→現在は「地域包括ケア病棟への直接入棟(A)→悪化に伴う自院の急性期病棟への転棟(B)→回復に伴う地域包括ケア病棟への転棟(C)」において、「Cでは地域包括ケア病棟入院料を算定できず、特別入院基本料」を算定するため、▼救急搬送患者の地域包括ケア病棟での直接受け入れの躊躇▼中小病院のベッドコントロール停滞—の原因となっている)
▽救急・緊急患者の地域包括ケア病棟での直接受け入れ割合が一定以上の場合、【在宅患者支援病床初期加算】の上乗せを行ってほしい(言わば「上位の地域包括ケア病棟の評価」「地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の中間評価」を求めるもの、関連記事はこちら)
→主に内科系の救急・緊急入院の地域包括ケア病棟での直接受け入れを促進し、【地域包括医療病棟】の届け出が難しい中小病院における「高齢者救急の受け入れ評価」による地域医療貢献が促される
▽短期滞在手術等基本料3について、地域の医療資源や訪問診療の充実度、手術環境などを考慮した柔軟なルールを設定してほしい(一律の「外来中心」への規制をすべきではない、関連記事はこちら)
→短期滞在手術等基本料を「外来中心にすべき」との意見もあるが、過疎地の高齢独居患者などは通院が困難なケースも多い
他方、2024年度の前回診療報酬改定で創設された【地域包括医療病棟】については、まだ若い入院料ということもあり、次の2点の要望を行うにとどめています。
▽重症度、医療・看護必要度に係る救済措置の期限延長、新たな評価軸の設定を行うべき
→現在は要件が厳格ゆえ、「軽・中等症の高齢者救急」を一定以上受け入れることは難しく、病院が届け出しやすい環境を整えるべき
▽高齢者救急を地域包括医療病棟に集約するのではなく、地域の医療ニーズに応じ「急性期一般病床+地域包括ケア病棟」、「療養病床+地域包括ケア病棟」のように、簡潔な組み合わせで転換を複線化すべき(関連記事はこちら)
→DPC参加基準を満たせない急性期病棟や、救急搬送受け入れに注力する地域包括ケア病棟から地域包括医療病棟への転換が検討されているが、中小病院には厳しい要件もあり、大都市や過疎化が進む地方都市では「急性期一般+地域包括ケア病棟」などのニーズが今後も継続し、過渡期的な対策として必要なケアミクスを認める必要がある
今後、こうした要望も踏まえながら中医協等で2026年度診療報酬改定論議が深められていきます。
【関連記事】
費用対効果評価制度、「保険償還の可否判断に用いない、価格調整範囲は加算部分のみ」との現行制度を見直すべきか―中医協
物価高騰・円安で「医療機器の逆ザヤ」(償還価格<購入価格)問題が拡大、2026年度材料価格制度改革での対応は?―中医協・材料部会
2026年度薬価制度改革に向けた論点が出揃う、イノベーション評価・皆保険の持続可能性・安定供給の3本柱—中医協・薬価専門部会
認知症治療薬レケンビの費用対効果評価、介護費縮減効果は勘案せず、2025年11月から薬価を15%引き下げ―中医協総会(2)
2024年度、自治体病院の86%が経常赤字、95%が医業赤字と「過去最悪」、大規模急性期病院では9割超が経常赤字—全自病・望月会長
2026年度診療報酬改定に向け「集約化すべき急性期入院医療の内容はどこか」などをより詳しく分析・検討せよ―中医協総会(1)
急性期入院医療の評価指標、包括期入院医療の評価指標、看護必要度における内科評価などをさらに詳しく分析・検討—入院・外来医療分科会(4)
診療報酬で医師働き方改革をどう支援すべきか、医師事務作業補助者の確保をどう促進すべきか—入院・外来医療分科会(3)
「人生の最終段階でどういった医療を受けたいか」の意向確認、身体拘束最小化をさら進めるために何が必要か—入院・外来医療分科会(2)
外科医不足解消に向け、「急性期入院医療・高難度手術の集約化」や「外科医の給与増」などを診療報酬で促進せよ—入院・外来医療分科会(1)
2026年度診療報酬改定や病院経営維持に向け、8月下旬の概算要求に間に合う形で政府に具体的な要望を行う—日病・相澤会長
地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の「中間評価」創設を、急性期病棟とのケアミクスは柔軟に認めよ―地ケア推進病棟協・仲井会長
効率的で質の高い入院医療提供のため、「病院・病床の機能分化、集約化」だけでなく「病院経営の維持」を実現せよ―中医協総会(1)
白内障手術など「入院」から「外来(短期滞在手術等基本料1)」への移行をさらに進めるために何が必要か―入院・外来医療分科会(4)
病院におけるポリファーマシー対策などの前提となる「病院薬剤師の確保」を診療報酬でどう進めていけば良いか―入院・外来医療分科会(3)
2026年度診療報酬改定、内科症例の看護必要度評価の見直し、地域包括医療病棟の施設基準緩和などを実施せよ—日病協
特定機能病院で「再来患者の逆紹介」が進まない背景に何が?連携強化診療情報提供料の要件を緩和すべきか?―入院・外来医療分科会(2)
2024年度の自治体病院決算は85%が経常赤字、95%が医業赤字の異常事態、診療報酬の大幅引き上げが必要—全自病・望月会長
地域包括医療病棟と急性期2-5のケアミクス、「内科が不利にならない」ような配慮等をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果評価制度で「介護費用」の取り扱いをどう考えるのか、評価結果を診療ガイドライン等にどう反映させるべきか―中医協
外来医療ニーズ減少の中で「クリニックの在り方」をどう考えるか、かかりつけ医機能を診療報酬でどう評価するか—中医協総会
2024年度薬価制度改革から1年余りで画期的新薬の開発進む、2026年度改革でもイノベーション評価医の充実を—中医協・薬価専門部会
救急患者の「高次救急→一般病院」転院搬送、受け入れ側の一般病院に対する経済的評価も検討してはどうか―入院・外来医療分科会(4)
DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)
看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)
一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)
院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)
2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協
看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)
早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)
2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会
骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協
健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)
かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)
生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)
外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)
骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協
2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)
包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)
療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)
回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)
骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う
地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)
病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協
物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協
2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長
社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議
社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審
【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)
ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)
「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)
新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)
物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病
物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議
少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協
物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協
社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審
ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)
2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)
2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会
リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)
2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)
2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会
医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医
2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体





